『寝ながら学べる構造主義』内田 樹(文春新書)2002年
「偏見の時代を生きるために」構造主義の考え方。
本書は、難解な構造主義の思想を、わかりやすくかみ砕いて解説している入門書です。
マルクス、フロイト、ニーチェからはじまり、ソシュール、ミシェル・フーコー、ロラン・バルト、レヴィ=ストロース、ジャック・ラカンとフランス現代思想家を網羅しています。
構造主義とは何か?
構造主義というのは、ひとことで言ってしまえば、次のような考え方のことです。
私たちはつねにある時代、ある地域、ある社会集団に属しており、その条件が私たちのものの見方、感じ方、考え方を基本的なところで決定している。だから、私たちは自分が思っているほど、自由に、あるいは主体的にものを見ているわけではない。
p25
各個人は、生まれつきの遺伝子準拠の能力(先天的能力)などがあって、それによって、個人の全ての性質が決定されているのではなくて、大部分はその母国語、生まれ育った環境、その時代特有の空気、所属するコミュニティなどによって、自動的に規定されてしまっているということですね。
多少は遺伝子等は影響しているかもしれないが、それよりも、とりまく環境によって構造的にそうなってしまっている。そしてそれは非常に合理的で、「何かを知らない」ということさえも、「知らずにいたい」という努力の結果であると説明しています。
自己同一性を確定した主体がまずあって、それが次々と他の人々と関係しつつ「自己実現する」のではありません。ネットワークの中に投げ込まれたものが、そこで「作り出した」意味や価値によって、おのれが誰であるかを回顧的に知る。主体性の起源は、主体の「存在」にではなく、主体の「行動」のうちにある。これが構造主義のいちばん根本にあり、すべての構造主義者に共有されている考え方です。
p32
ヘーゲル、マルクスの労働観においても、人間は生産=労働によって作り出されたものによってしか、自分が何者であるかを知ることはできない。としています。つまり、ネットワーク(構造)のなか、関係性の中にしか個人の能力は存在しないということです。
個人が自分の中に深く入り込み、自己分析していっても、そこにも何もなく、互いのキャッチボールのような枠組みの中で、その場、その場によって変化する。マインド・セットとしても、現代の柔軟な働き方を支える考え方になっています。
名前のあるものしか存在しない
名づけられることによって、はじめてものはその意味を確定するのであって、命名される前の「名前を持たないもの」は実在しない、ソシュールはそう考えました。
p62
名前をつけることによって、はじめて世界から分節され、思考する対象として存在しはじめます。名前がつけられていないものは、そもそも思考する対象にすらならず、誰もそれを意識することができない。
たとえば、「肩が凝る」という表現をするのは、日本人だけで、アメリカでは「背中が痛む」と表現するそうです。英語では「重荷を背中に背負う」、「背骨を折る」など仕事のストレスを背中で受け止め感じとっている。なので「肩が凝る」という表現一つとっても、それは単なる身体的な痛みの表現ではなく、共通した了解があるからこそだと著者は主張しています。
自分が当たり前に思っていること、話し方、行動、選択も、実は、生まれ育った環境や、家族、友人、学校、職場によって決定されているかもしれない。と考えると、少し日常を見る視点が変わってきますね。
さらには、何に関心を持ち、何を知っていて、何を知らないかさえも、自分や自分が帰属している社会集団によって無意識的に選択させられているとわかると、いろいろな人に寄り添った柔軟な考え方ができそうな気がします。

寝ながら学べる構造主義 (文春新書) [ 内田 樹 ]
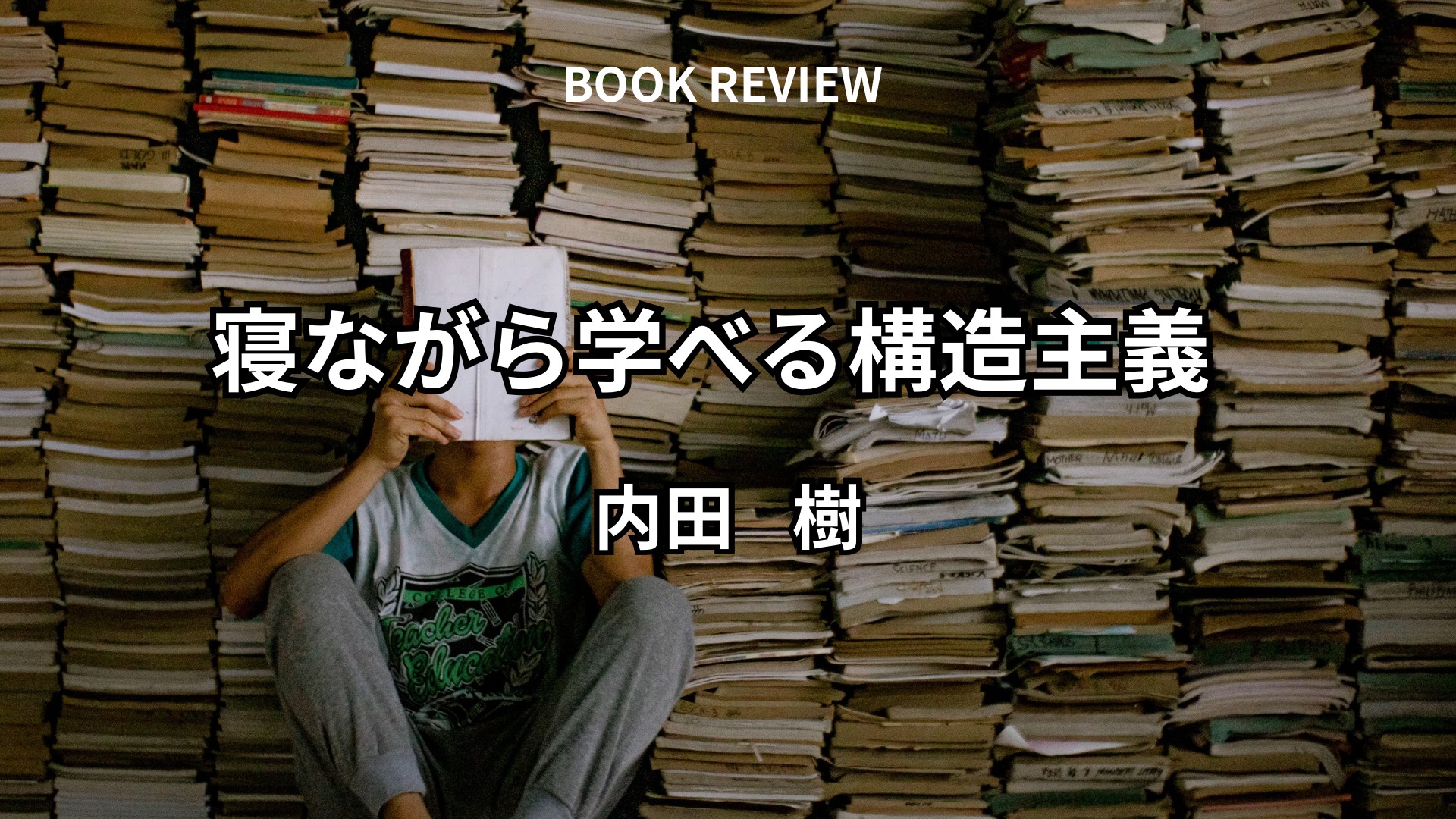
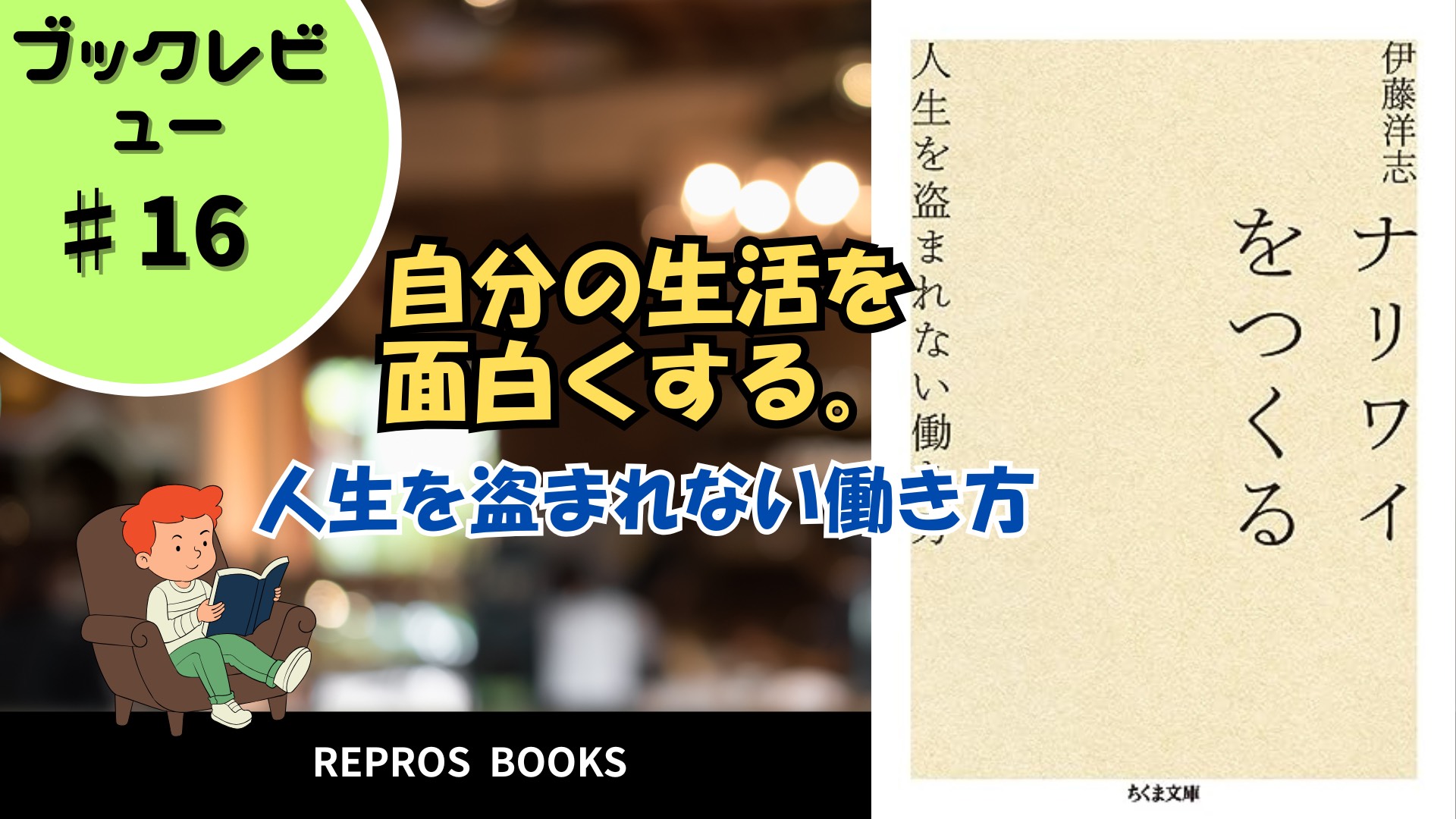
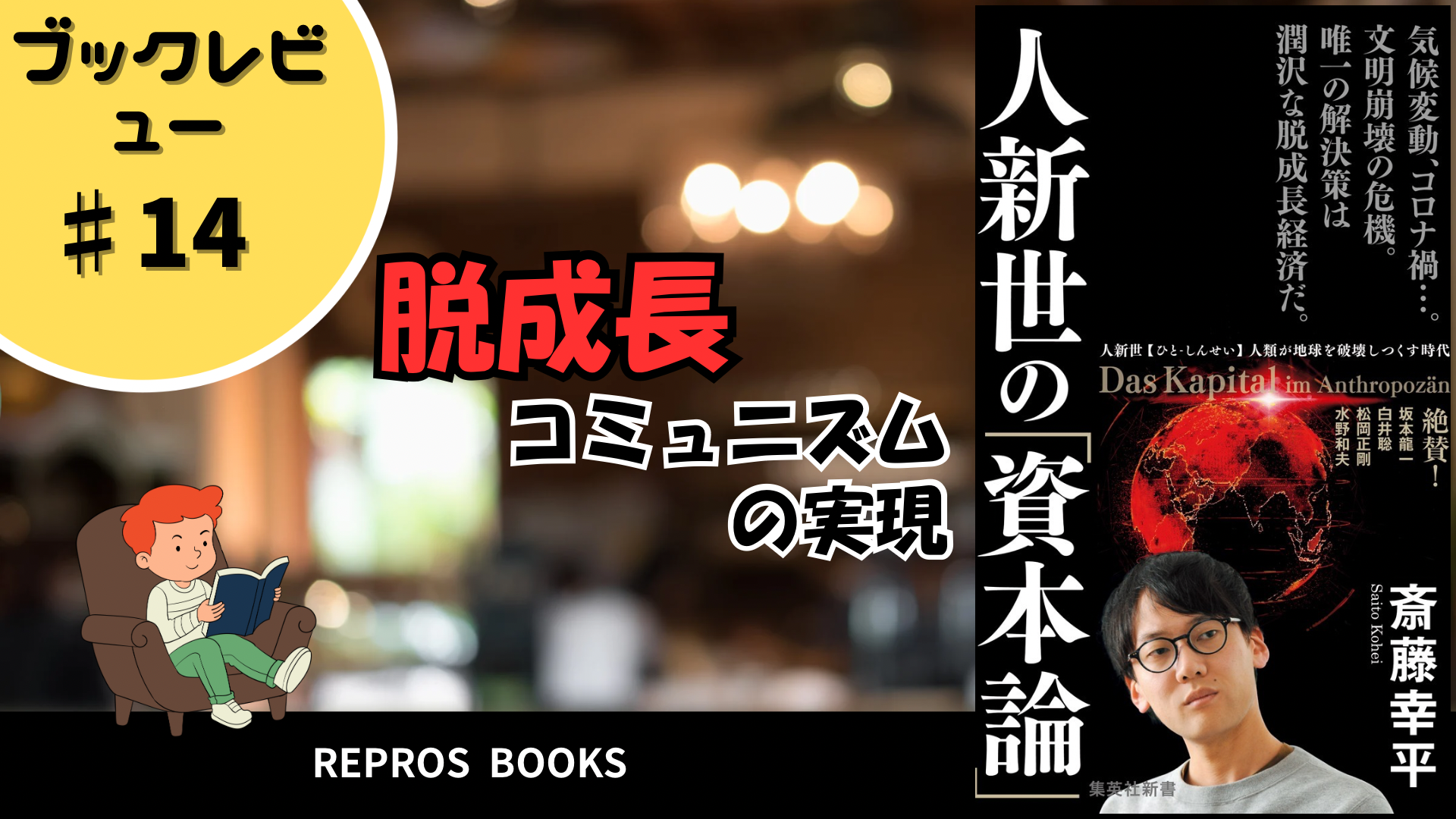
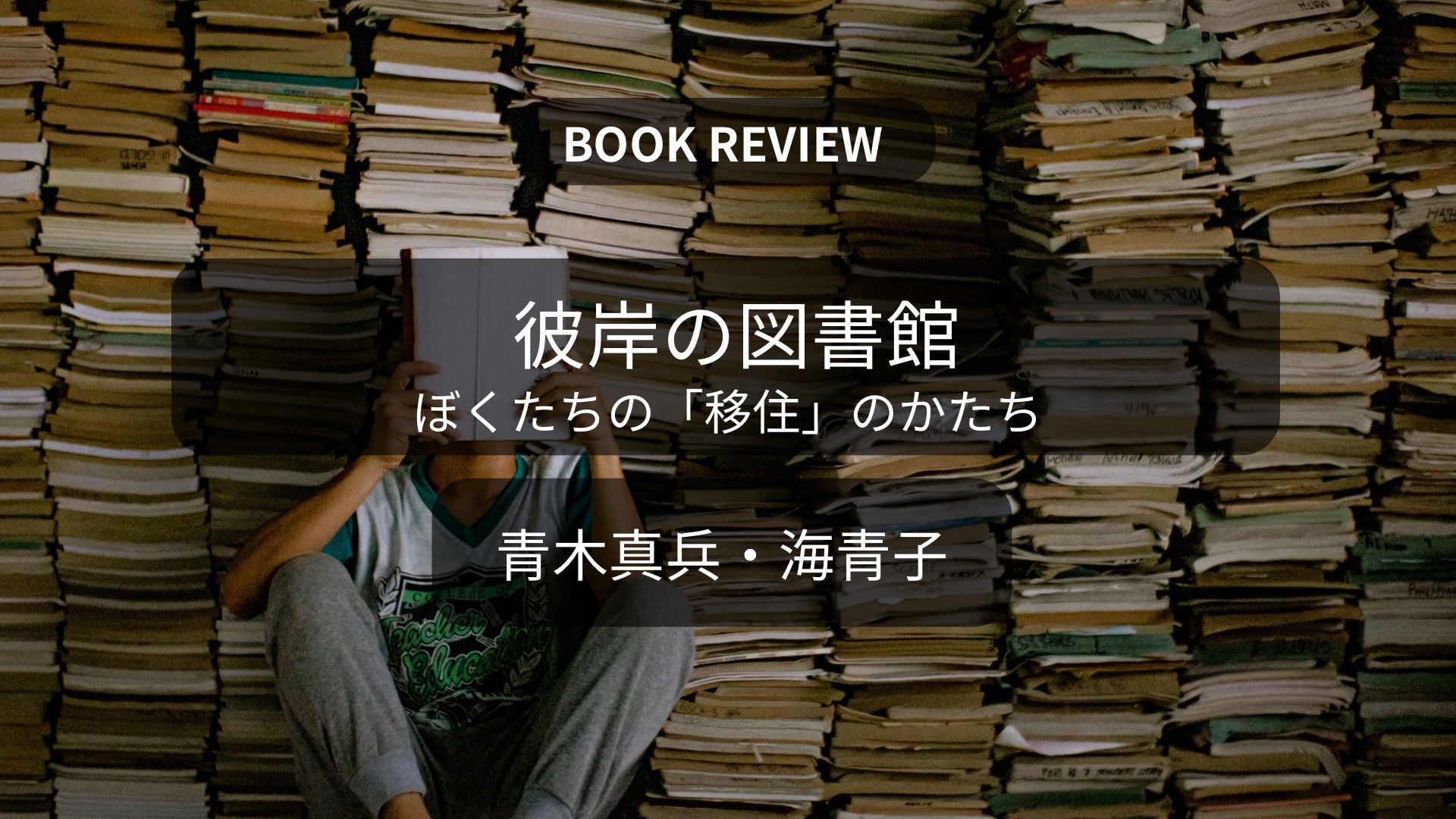
コメントを送信