『路地裏の資本主義』平川 克美(角川SSC新書)2014年
成長は矛盾の先送り「路地裏経済の再生」
資本主義、貨幣のまぼろし
資本主義とは何か?
と考えたときに、意外と明確な答えができなかったりします。
私たちは、資本主義経済のなかにどっぷりつかって生きていますので、資本主義経済に対する考え方の盲点も多いです。本書では、何が当たり前で、当たり前ではないか。という切り口から、貨幣、贈与経済、株式会社、定常経済など様々なアプローチで資本主義を解き明かそうとしています。
貨幣の万能性を担保しているのは、貨幣に対する信用だけなのです。逆に言えば、貨幣が貨幣であるためには、それを使う人間が貨幣には他のいかなる商品とも交換可能であるという貨幣の万能性に対する信仰の手助けがいるのです。
p38
皆が価値あるものとして貨幣を受け取り、未来の人間も間違いなく価値あるものとして受け取るという信仰があってこそ、貨幣は流通します。
経済学者の岩井克人『貨幣論』(筑摩書房)のなかでも、「貨幣が貨幣である理由はそれが貨幣として流通していること」(p103)とあるように、貨幣や資本主義の制度を支える根拠は、実はまぼろしのような、脆いものなのかもしれません。
養老孟司さんとラジオの番組でお会いしたとき、大変興味深いお話をされたのを覚えています。
「文明とは秩序であり、秩序とは変化しないものをつくり出すことであり、それには、変化そのものである自然をコントロールするか、人間の社会そのものをコントロールして自然との折り合いをつけるかの二通りの方法がある」と言われたのです。
p47
自然をコントールしようとすることは、自然を破壊することにほかならず、それは人間の経済活動が地球環境を大きく変化させているという時代、「人新世」と呼ばれる言葉にも象徴されています。
過剰に商品を生産するということは、それだけゴミも大量に生産することに繋がります。しかし、それは、近代国家が経済成長するにあたって、当然に予測されていた帰結です。
路地裏の資本主義
第二章では、喫茶店が消えた理由をめぐり、1970年代を回想しています。
喫茶店の椅子に座ってボーっと半日を過ごすような人間が生きていくのが、難しい時代になったということです。当時のわたしが、今を生きていることを想像すると、アルバイトの収入では食べるのがやっとで、コーヒー代を払って無為の時間を過ごす余裕は、どこを探しても見つからないように思えます。
あの頃は、何であんなに余裕があったのだろうかと不思議です。喫茶店主にしても、お客にしても、非効率のモデルのような場所が喫茶店だったのです。
p71
1980年代半ばには、土地価格の上昇により、喫茶店は次第に姿を消し、チェーン店やコインパーキングに代わっていったそうです。それ以上に、日本人のライフスタイル自体が、「非効率」を過ごす余裕を消し去っていったとしています。
さらには、コンビニエンスストアの出現により、お金さえあれば一人で生きていける環境が作られ、友人、家族、地域の助けがなくても、アノニマスな消費者としてのみ存在することが可能になってしまったと著者は語ります。
マルセス・モース『贈与論』
また、両親の介護を通して「わたしは、わたしのために生きているのではない」という気づきを得て、マルセス・モースの『贈与論』を参照しています。
そこには、何かを贈られた当事者は、相手に返礼するのではなく、それを第三者にパスしなければならない。第三者から当時者にそのパスは別のかたちで戻され、再びかたちを変えて元の贈り主へと返さなければならないというマオリの習俗について書かれていました。
p89
マオリの不思議な交換を統御しているのは「ハウ」とよばれる霊力のようなもので、現実的にいえば知恵の掟のようなものであるとしています。
第三者への贈与が、社会そのものを存続させるマナーになっているともいえます。
ぐるぐる循環していくシステムだけが、継続性を持ったシステムであり、日本でいえば、田舎の商店街や、顔見知りの小規模店、地縁などがまさにそれでした。そこには、もちろん爆発的な経済成長も、効率性もありませんが、確かな豊かさがあったのだと思います。
二つのフィクション
近代社会は、国民国家というフィクションと、株式会社というフィクションの上に発展してきました。留意しなければいけないのは、この二つのフィクションの上でつくられてきたさまざまな制度は、すべて経済が右肩上がりに成長し、文明が都市化へ向かって進展するという背景のもとに考案されてきているということです。
p164
年金、保険、貯蓄制度、住宅ローン、ありとあらゆる制度設計が、経済が右肩上がりに成長していくことが大前提になっています。子供がたくさん生まれ、消費は拡大し、GDPは増加し続ける。有限の地球の資源の中で、あたかも無限にも近い枠組みで制度設計がなされていることは、矛盾や問題を永遠に先送りしているような感覚です。
成長を止めてみること。立ち止まることが重要になってきます。
ただし、国民国家というフィクション、株式会社というフィクションの、(もしかすると、貨幣というフィクションや、資本主義というフィクションも加わってくるのかもしれませんが、)制度設計が限界にきていて、今にも崩壊しそうであるならば、我々は一体どうすればいいのか?という問いの答えは本書には書かれていません。
共生型の定常経済モデルが具体的にどういったものなのか、どういう形が理想なのか。全面的な移行はどうすればいいのか。議論する余地を残しています。

路地裏の資本主義【電子書籍】[ 平川 克美 ]

贈与論 (ちくま学芸文庫) [ マルセル・モース ]

貨幣論 (ちくま学芸文庫) [ 岩井克人 ]
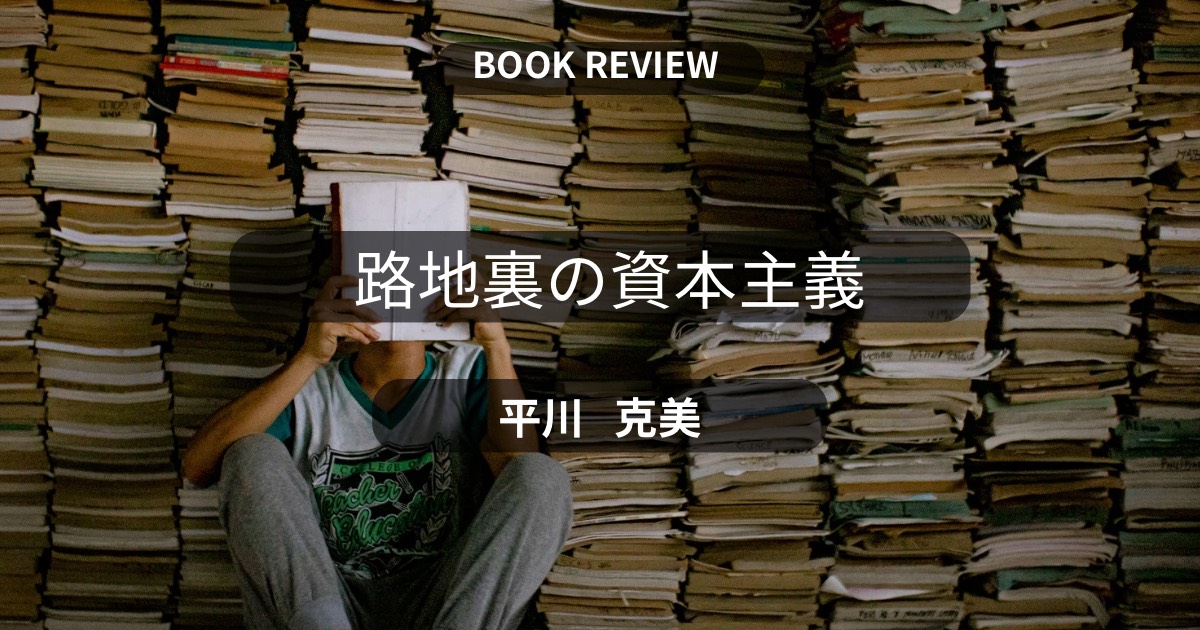
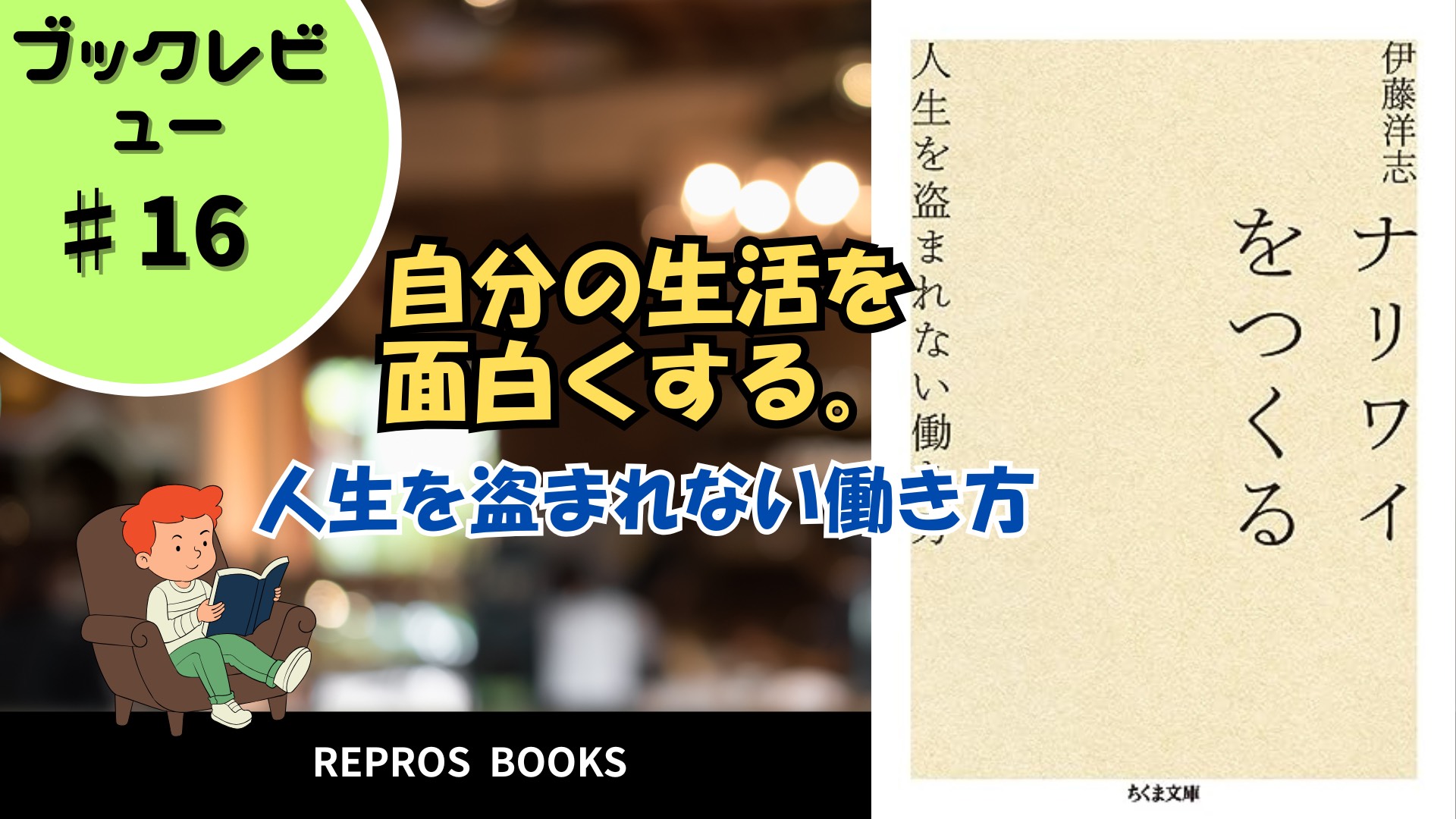
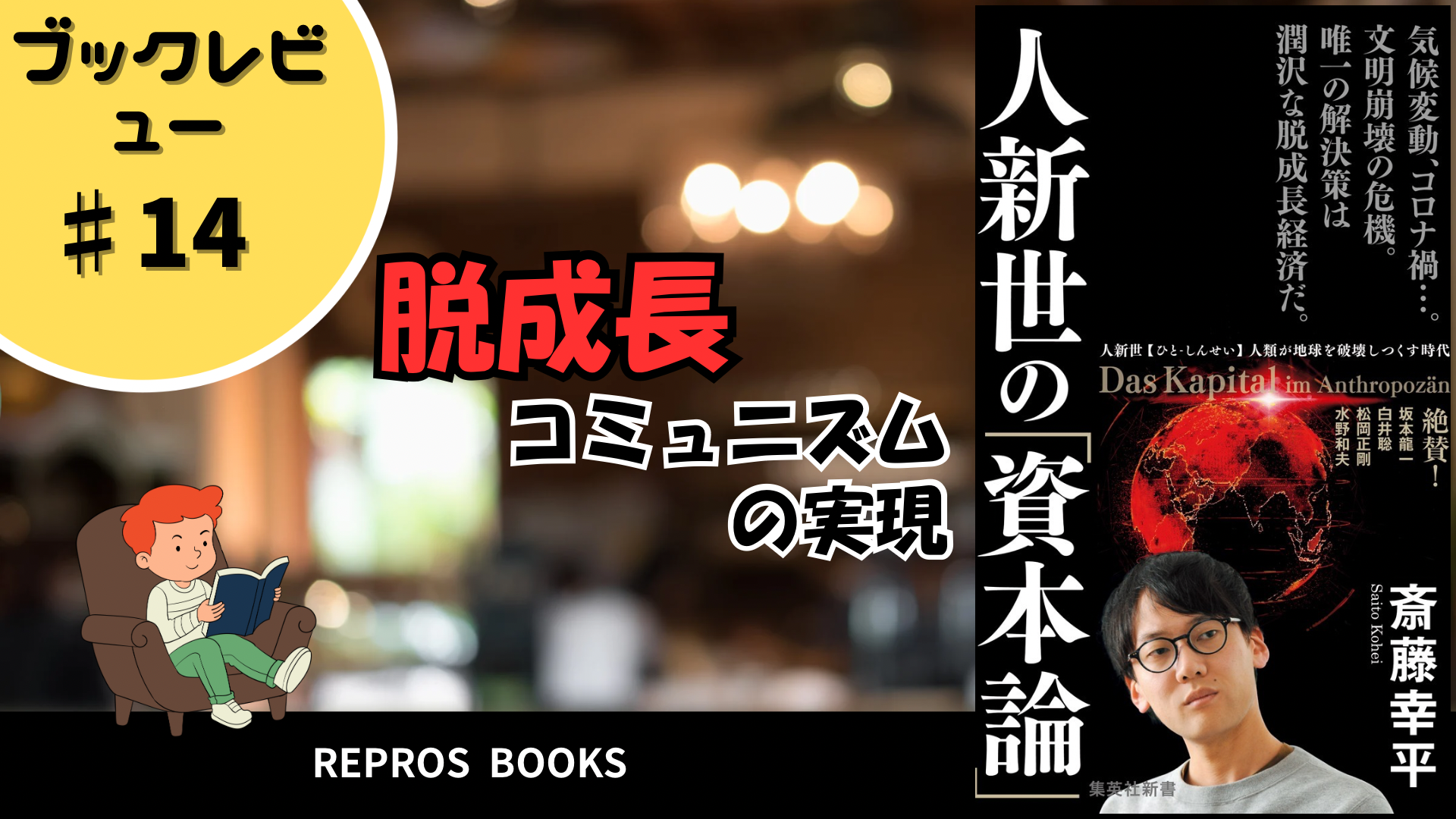
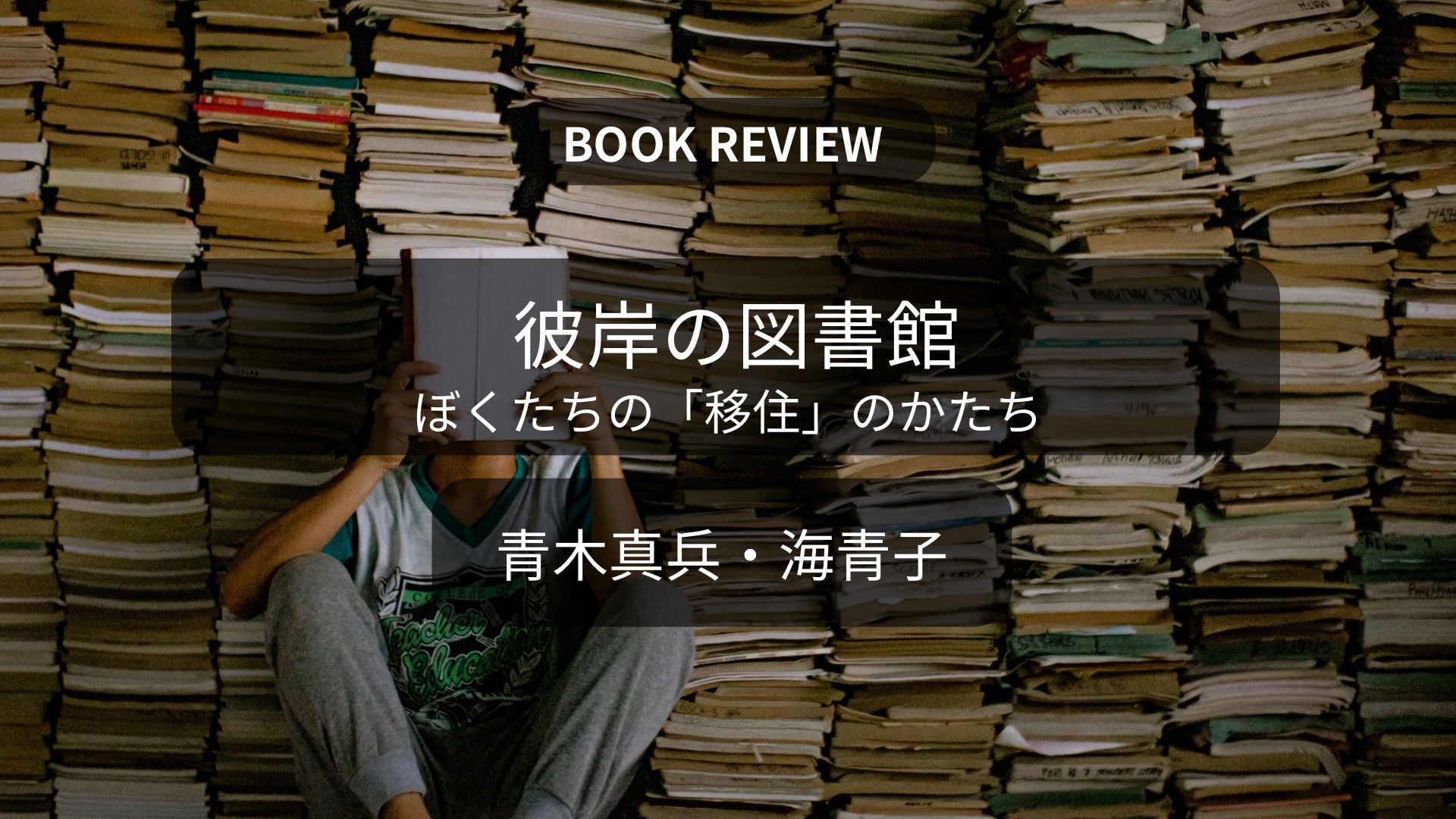
コメントを送信