『寂しい生活』稲垣えみ子(東洋経済新報社)2017年 / (幻冬舎文庫)2024年
役に立つとは何か?
家電を捨てる
東日本大震災の原発事故をきっかけとして、家電を捨て、最終的には仕事も捨て、ものすごくシンプル=寂しい生活を送っている稲垣えみ子さんの著書。朝日新聞社で記者として勤め、2016年にちょうど50歳で早期退職されているので、仕事を辞めてわりとすぐに出版した本です。
断捨離やミニマリストとはまた違った角度から、電灯、ラジオ、パソコン、携帯以外の家電を捨て、反・物質生活を実現しています。
世の中は自分の思うようには進まない。
頑張っても物事がうまく運ぶとは限らないし、たとえうまく運んだところで自分が望むような評価が得られるとは限らない。もし奇跡的に評価されたとしても、それは瞬く間に過去のこととなり、またすぐに試練と評価にされされる日々が待っている。
p134
著者はブッダの教えから、未来や過去にとらわれず、いまを生きること。に気づきつつ、その難しさに困惑しますが、冷蔵庫を捨て、買い物の楽しみを奪われることによって、いまを生きること。の根源にあるものを理解します。
人は絶えず「いつか」食べるものを買うようになったのである。しつこいようだが、人が食べられる量には所詮は限界がある。だからその多くは廃棄されることになる。簡単に言えば「食の買い捨て文化」を冷蔵庫が作り出したのではないだろうか。大量生産・大量廃棄。これが経済を回してきたのである。
p143
食べるためにだけにあったはずの「食べ物」が、冷蔵庫の誕生により、「買いたいという欲」、「食べたいという欲」を無限に溜めるこむ装置になってしまっており、人間本来の生きていくことの本質を見えなくしてしまった。と著者は指摘します。
モノの所有では解決できないこと
モノは結局のところ人を救うことはできないではないでしょうか。消費社会とは、モノを売ったり買ったりすることができる健康で強い人たちのためのサークル活動です。それは一方で、本当に救いを求めている人たちをはじき出していく会員制クラブに成り果てている。
p271
あまりにも世の中に、便利なものが溢れてしまった結果、人の欲望や心理を巧みに操り、次々と便利機能をつけて、さらなる消費へと駆り立てます。毎年、新製品が登場するパソコン、洗濯機、掃除機、冷蔵庫。毎年、バージョンアップするiPhone。
これは実体がある商品に限らず、言葉や概念によるパッケージ化に関しても同様だと思います。毎年、次々と新しいビジネス用語による、横文字を言い換えだけの新しいサービス。
家電を捨て、便利な生活を辞め、仕事を捨てた著者は、それらを捨てた分だけ、別の物が入ってきたと言います。それは、身の回りの人の関係だったり、季節を感じとるセンサーだったりします。モノの所有や便利さによっては、逆にその自然な感覚を阻害し、見えなくさせます。
役に立つとは
役に立つ時間というのは、人から評価され、お金になる時間です。逆に、役に立たない時間とは、人から評価されず、お金にならず、さらに面倒くさいことです。商品(家電)やサービスは、役に立つ役割を引き受けたかのように見えますが、実際はそうではなく、不毛な能力主義社会へと突入させます。
なぜなら老いて死んでいく時、人は誰もが「役に立たない」存在になっていくからです。いや老いて死ぬ時だけじゃない。病気をしたり、怪我をしたり、あるいは仕事に失敗したり、人から拒絶されたり、いろんな局面で、人はいつだって「役に立たない」存在に転落していく。だからこそ、そうなりたくないと思ってみんな懸命に頑張っているんだ。
p290
面倒くさいことをやることによって、いままで見えなかった世界が見えてくるかも。そんな不思議な感覚にさせてくれる一冊です。

寂しい生活 [ 稲垣 えみ子 ]
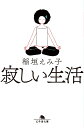
寂しい生活 (幻冬舎文庫) [ 稲垣えみ子 ]
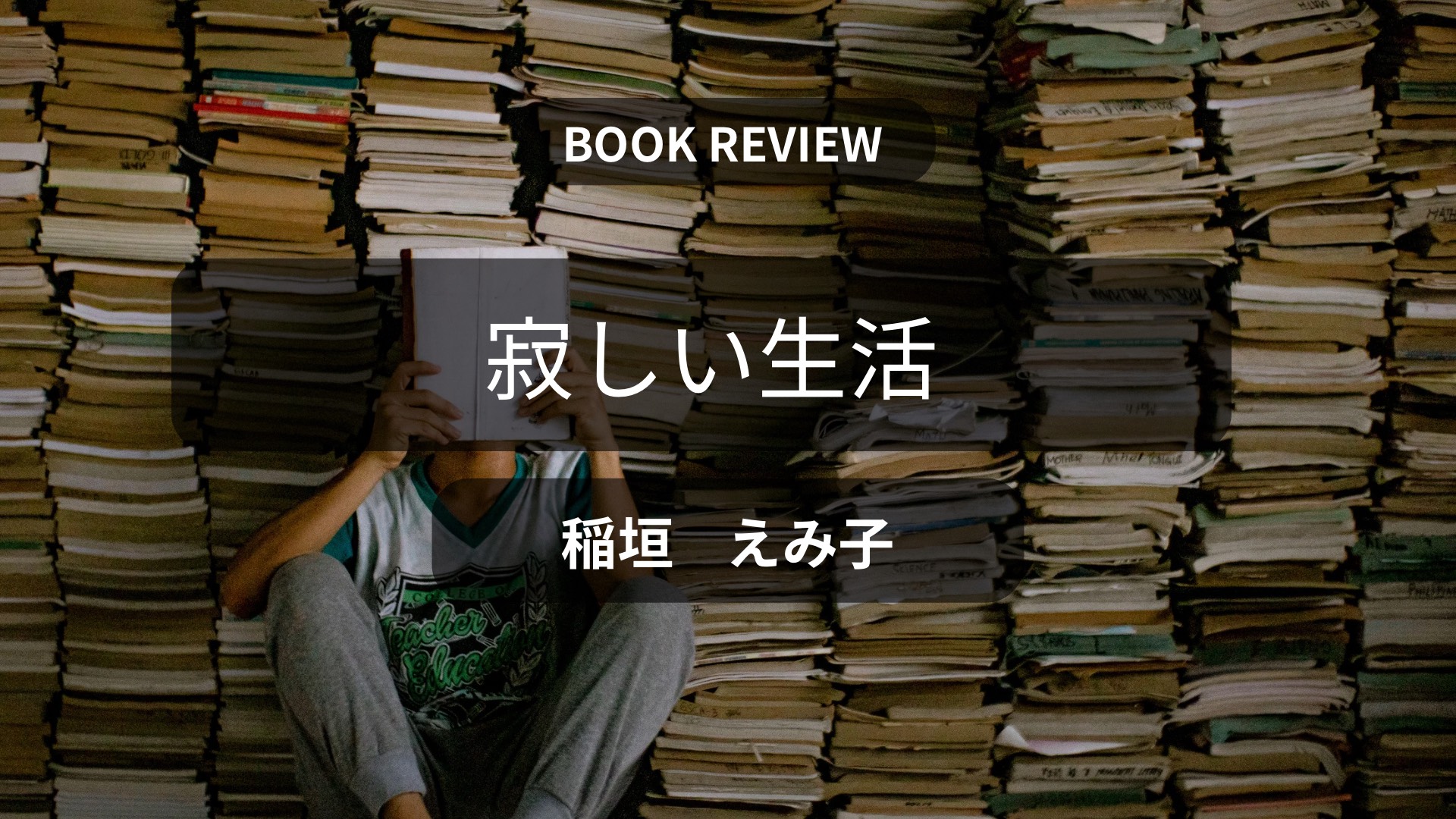
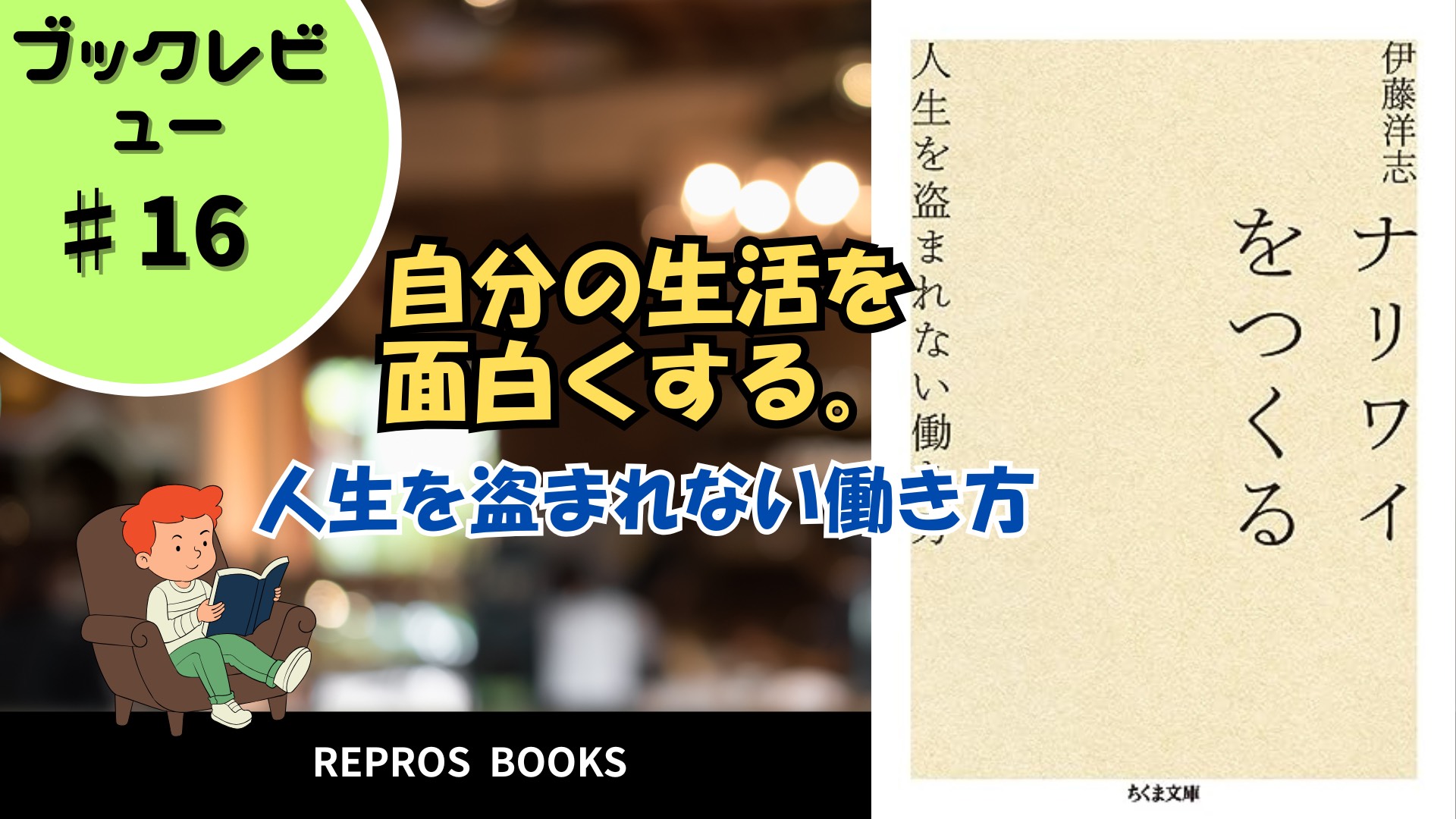
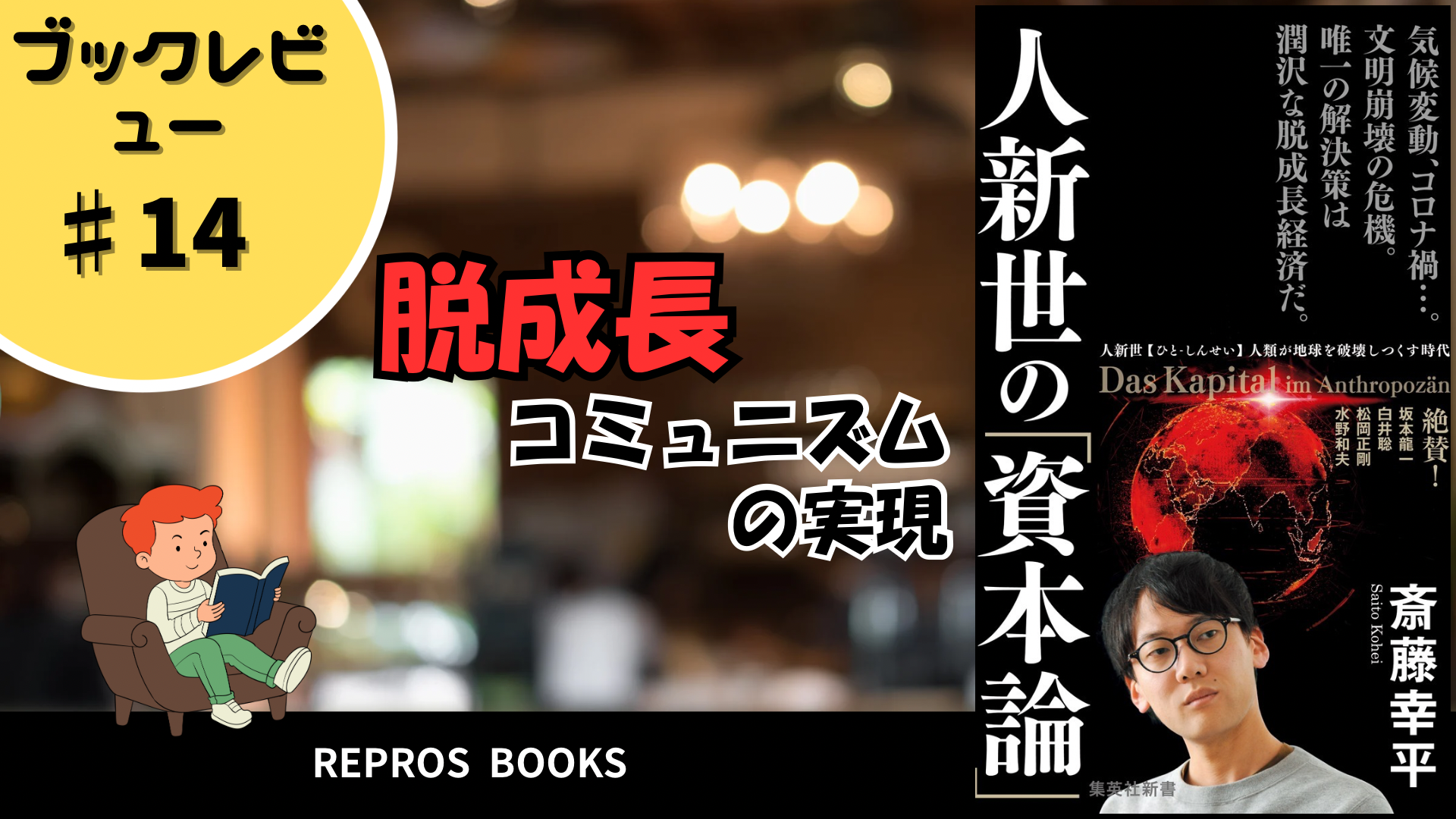
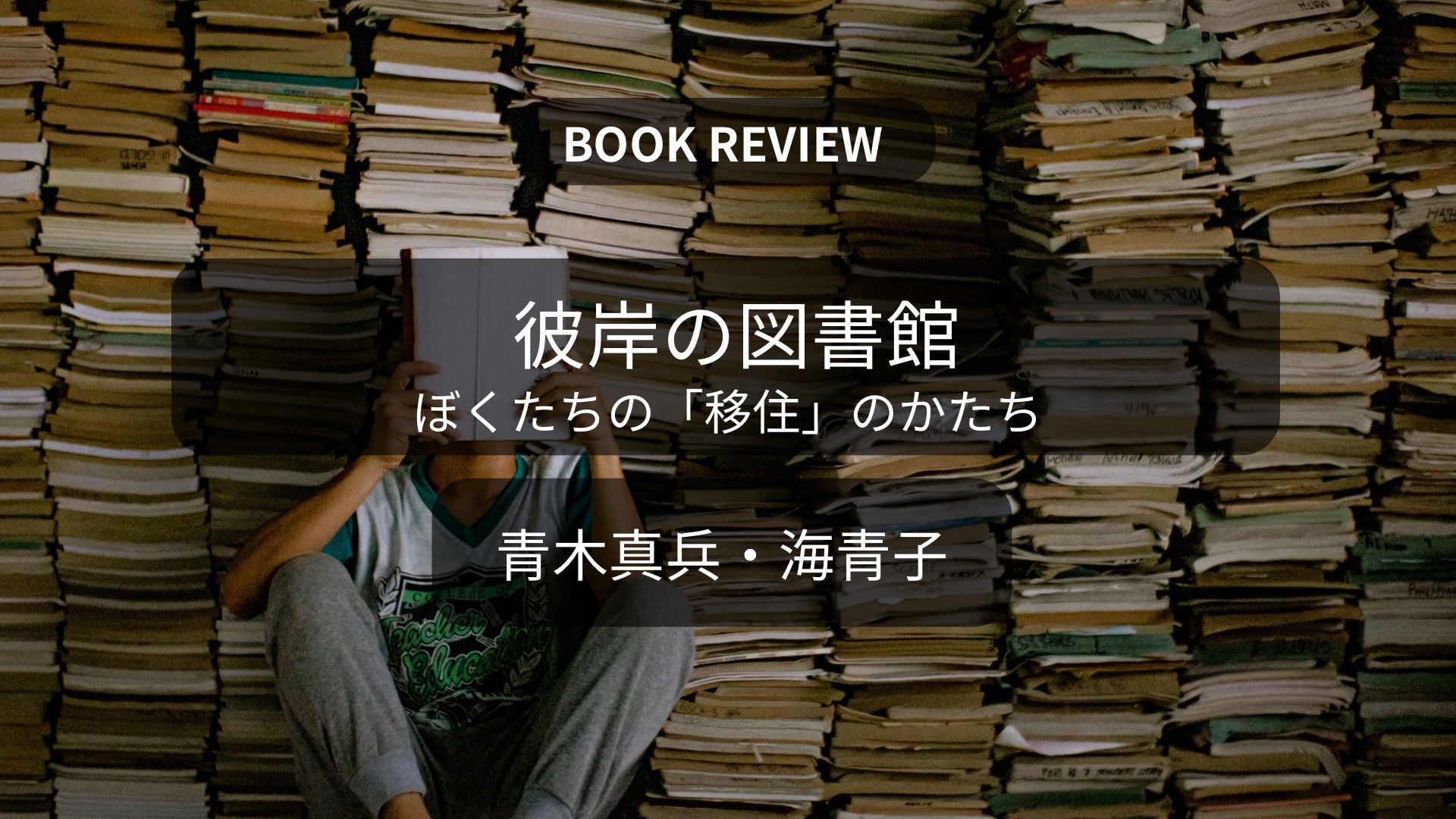
コメントを送信