『苦しかったときの話をしようか』森岡 毅(ダイヤモンド社)2019年
働くことの本質
人生を自分でコントロールする”選択肢”
著者が、大学生の子供のために書いた『虎の巻』が本書のベースになっており、仕事に対する考え方(フレームワーク)、本人に認識できる世界(パースペクティブ)を体系化した内容となっています。文章も、まだ若い学生に語りかけるようなスタイルになっています。
著者の経歴としては、新卒でP&Gに入社後、経営危機にあったUSJをV字回復させ再建。USJ関連の話、何冊かでている別の書籍に書かれています。
これから就職活動をする学生の方はもちろん、社会人1年目、2年目と比較的、入社したばかりの方や、これから転職や起業をしようと目論んでいる方にも有益な情報が詰まっています。キャリア自体はかなりハイスペックな話になるため、あまり一般的な感覚での参考にはなりませんが、精神論というか意気込み、視座みたいなところは、多くの方にとって参考になるのではないかと思います。
人生のコントロールする選択肢を持っているのは、自分自身しかいない。この選べる、選択できるということすら、環境によっては忘れてしまう。もしくは馴れてしまう。そうならないための道筋を見つけるには何をしたらいいのか? ということについて重点的に書かれています。
教育と資本主義
よく考えれば、日本の教育システムも、大量の優秀なサラリーマン(労働者)を生産するように作られている。良い大学を出て、大きな会社に入って、安定した生活を送る、それが幸せな成功者の目指す道だと。昭和の高度経済成長時代の”呪い”はまだ色濃く残っていて、今も多くの人のパースペクティブだ。
p62
著者は、給与所得の最高税率は5割を超えるが、株式配当の税率は2割しかかからないなどの例をだして、サラリーマンの外の枠組み、資本家という存在が、資本主義社会においては最優先されるということを強調しています。そして、学校教育は資本家を作り出す教育ではなく、優秀なサラリーマン(労働者)を作り出す教育をしていたと。
本書が刊行されたのが2019年ですが、2025年現在では、昭和の高度経済成長時代の”呪い”は、少しだけ薄れてきたように思います。とりわけ若い世代は、この”呪い”の影響を受けておらず、新たな感覚で自分の価値観に基づいた職業選択や生活を送っているように見えます。就職氷河期を経験した40代以上の親世代が、この最後の”呪い”が直撃した世代です。そして、新入社員として就職、または派遣社員やアルバイトで組織の中でずっと働き続けていると、古い感覚だけが残り、それを絶対視していしまいます。
また、IT業界などには、学生時代に長年引きこもり生活を送っていた後、経営者となり活躍されている方が数多くいます。社会や世論に流されず、好きを強みに変えて、プロフェッショナル化できたことが要因だと思います。
ゼネラリストとプロフェッショナル
避けた方が良いのは君にどんな職能が身につくのか想像がつかない会社だ。その会社の30歳前後の人に何人か、どんな職能を持っているか、今どんな権限で何の仕事をしているか、聞いてみたら良い。明快な答えが返ってこないのであれば、それはプロを育てない組織である可能性が高い。実際に多くの企業のシステムはそれに近い状態になっえいるから気をつけねばならない。会社から割り振られた仕事を黙々とやり、適当にローテーションされながら、広範囲を知るゼネラリストをつくると言われても、真実はどの領域においてもプロではない中途半端な人材を大量生産させてしまっている。
p147
プロを育てない組織に身をゆだねてはいけない。自分で自分の強みを磨き、プロとしてキャリアを自律していかなければならない。自分の強みというのは、自分の好きな分野に必ずあるので、そこにとにかく集中すること。と著者は語ります。
小さなパイのなかでシェアを争うしかない現代においては、社会全体が右肩上がりに成長していた時代と根本的に異なり、ゼネラリストという職能では対応しきれません。
”キャリア”に対する個の覚醒が必要なのだ。シンプルに言えば、やりたいことを考えないことや我慢することがデフォルトになっている社会を、それぞれの”欲”に対して素直に旗を立てて進むことが当たり前になる社会に変えることだ。
P302

苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」 [ 森岡 毅 ]
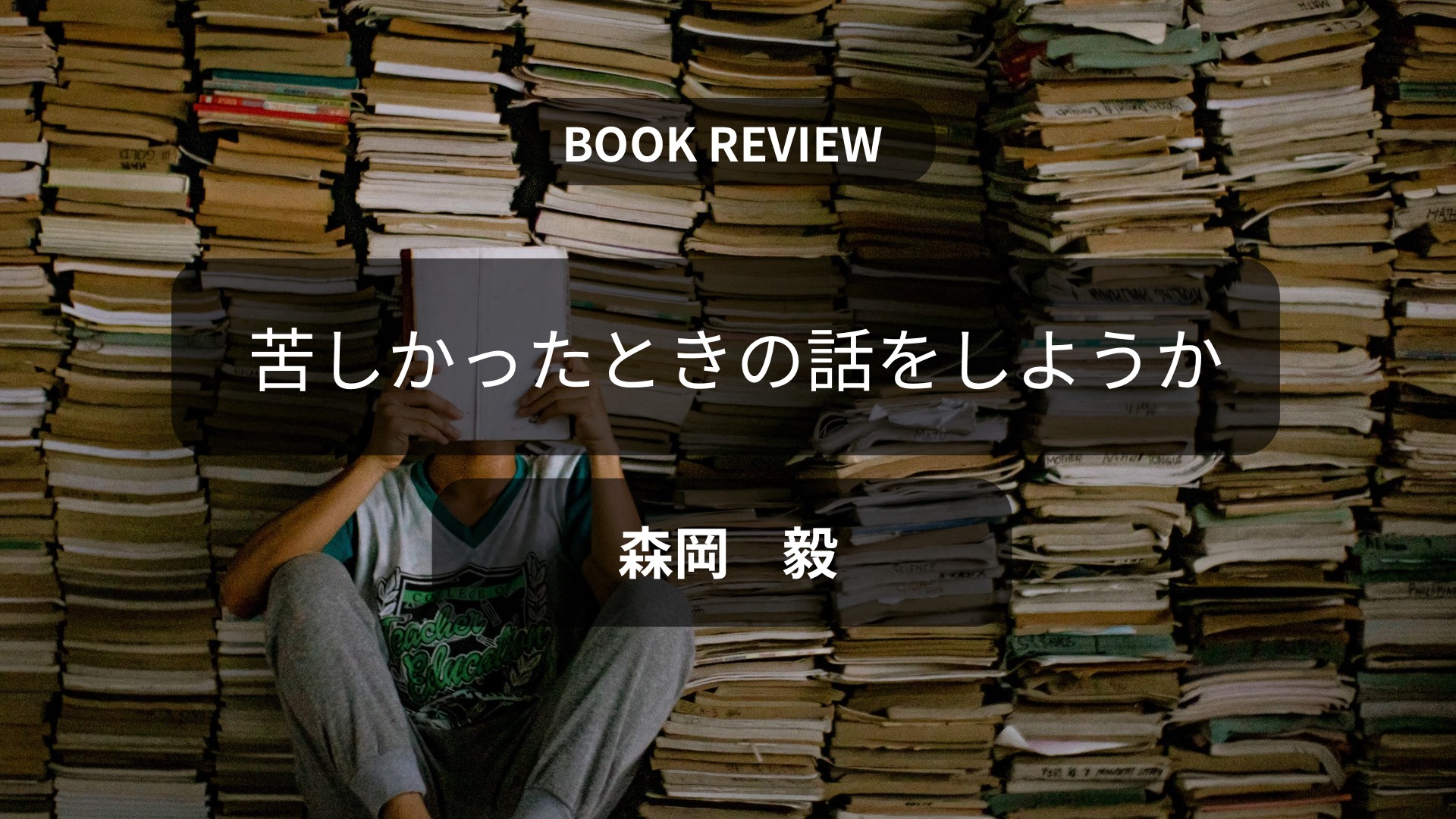
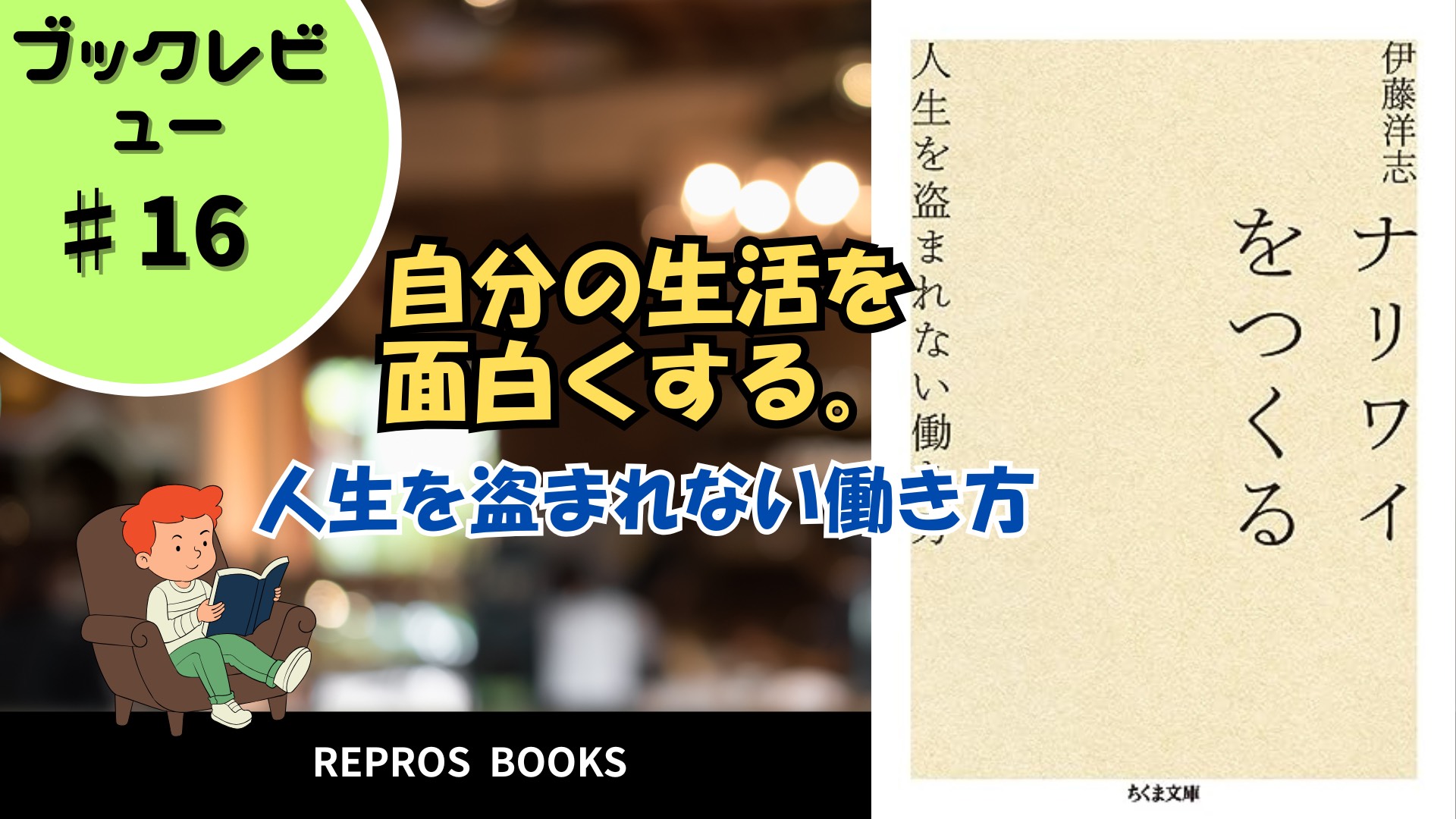
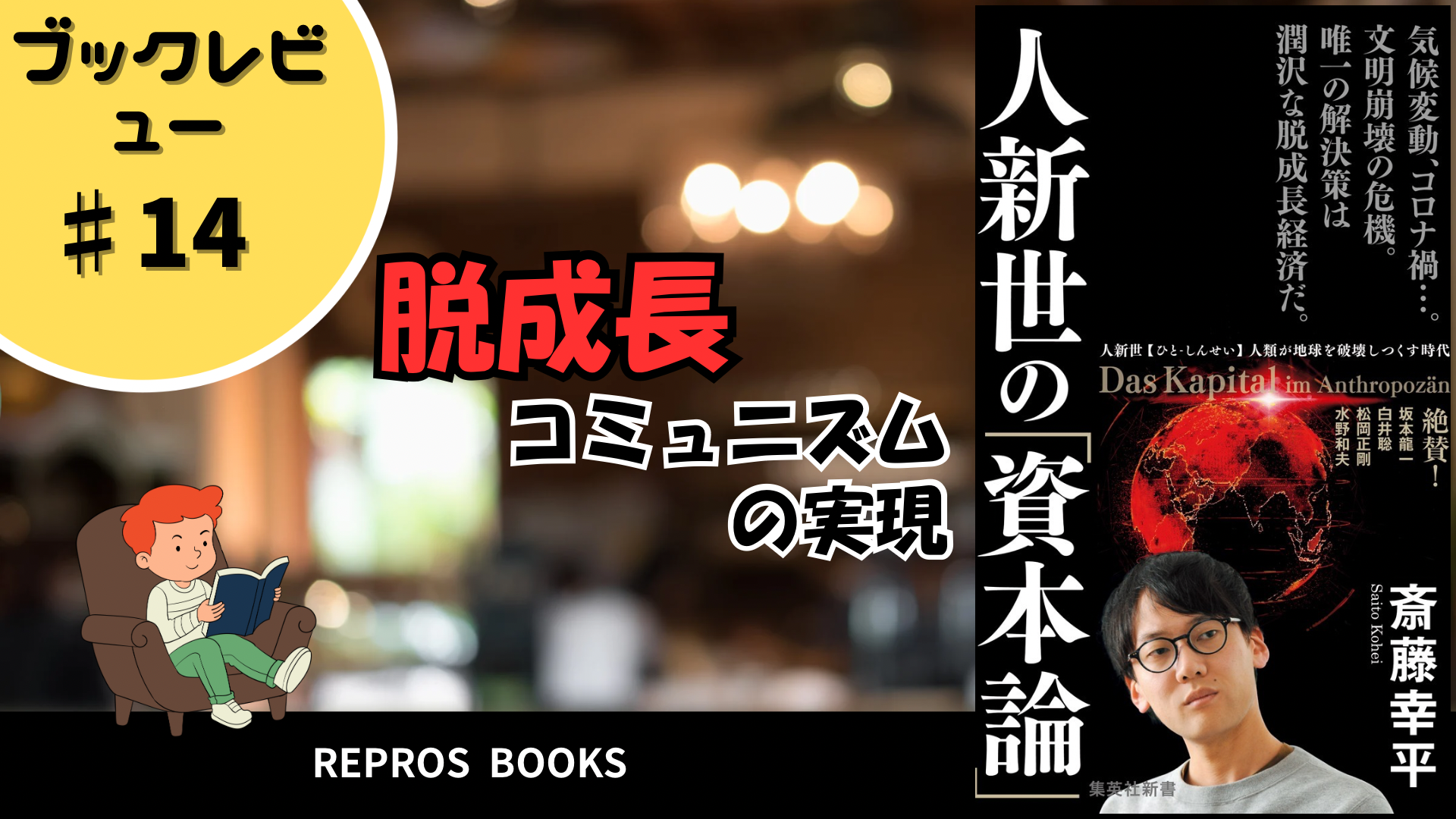
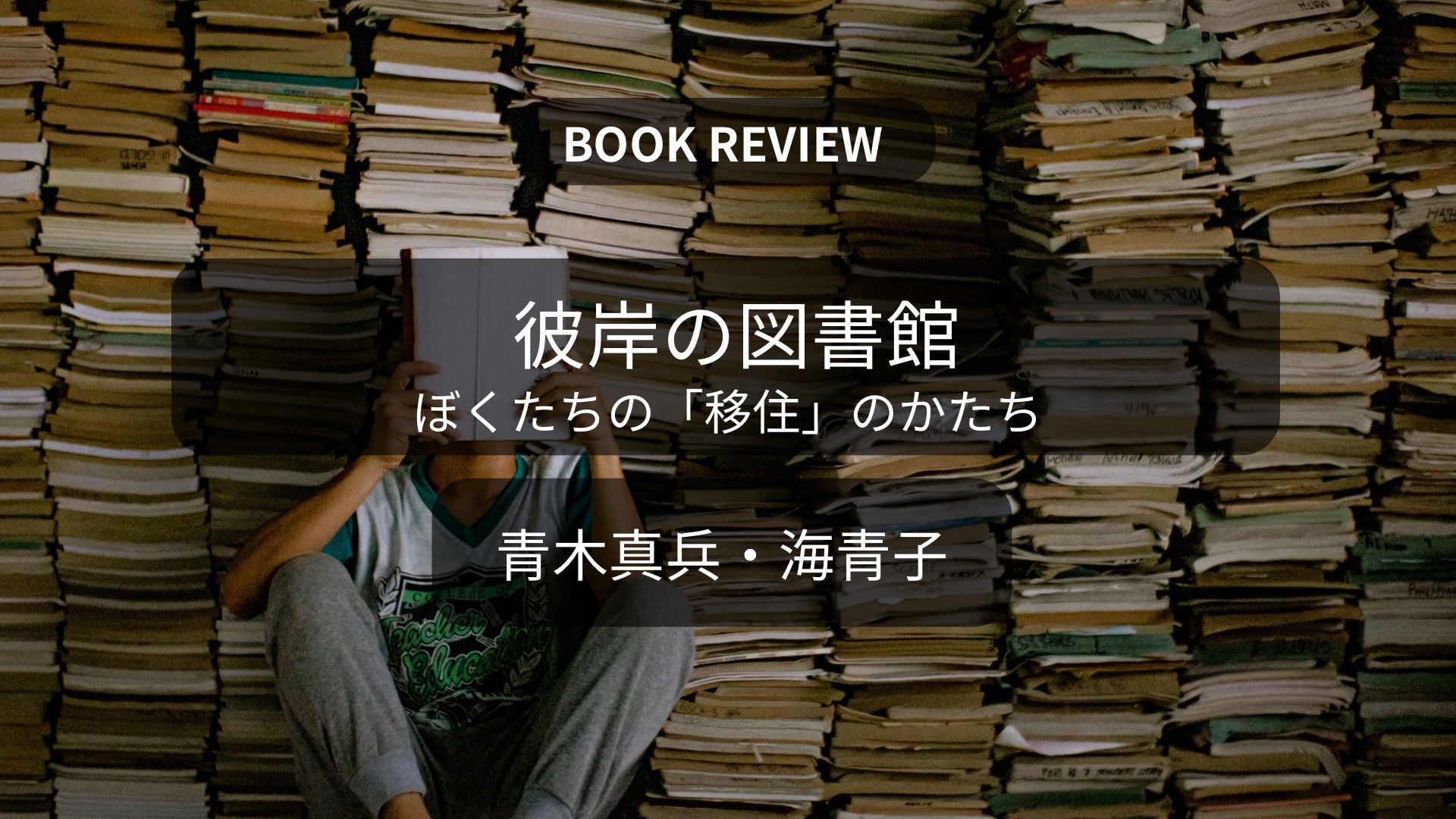
コメントを送信