『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』しんめいP(サンクチュアリ出版)2024年
10代でも読める東洋哲学の入門書
無職の哲学エッセイ
虚無!
32歳。無職になり、離婚して、実家のふとんに一生入っている。
p2
仕事を辞め、離島での教育事業も辞め、いきなりはじめた芸人も辞め、しまいには離婚してひきこもった結果、執筆に至った東洋哲学の本です。もともとはnoteの『東洋哲学本50冊よんだら「本当の自分」とかどうでもよくなった話』という1本の記事だったようですが、そこから3年半かけて、本のボリュームまで膨らませたそうです。
ブログのような形態で読みやすいですが、文字の密度が低いので、逆に受け付けない方もいるかもしれません。それでも、ふざけているようで、ふざけていない、核心をついた文章は読みごたえがあります。東洋哲学に興味がある中高生にもお勧めです。
1章 無我 ブッダ
2章 空 龍樹
3章 道 老子と荘子
4章 禅 達磨
5章 他力 親鸞
6章 密教 空海
以上の7人の哲学者の考えを知って、虚無からどうやって回復したかを綴っています。
空と縁起
この世界はすべて「空」である。
どういうことか。
龍樹のことばを紹介しよう。(この世のすべては、ただ心のみであって、
あたかも幻のように存在している。
『大乗についての二十詩句篇』18)すべては「幻」である。こういいかえてみよう。
この世界はすべて「フィクション」である。ということだ。
「フィクション」。このひとことで、ブッダの「自分がない」の意味が、超クリアになるのだ。
p62
言葉や概念のフィクション性を非常にわかりやすく説明しています。たとえば、会社や国家や、町や、家族ですら、言葉によってつくられた虚構にすぎない。幻にすぎないとしています。
「縁起」=ぜんぶつながっている。境界線がない。
言葉や概念によって世界を分節しているので、会社、国家、町、家族などを分解していくと、実体があまりない。根拠がない。ということはよくある話だと思います。突き詰めていくと、基準や根拠がよくわからなくなる。
大本にいくほど、曖昧な基準になっていくという現象です。
禅
「禅」の教義は、「言葉をすてろ」のひとこと。
これを「不立文字(ふりゅうもんじ)」といいます。
言葉で説明できないものを、言葉で説明する。
それ自体が自己矛盾であって不可能な話です。著者は悩んだ挙句、苦肉の策としてつかった手段は、白紙です。なんと印刷ミスのような完全な白紙ページが数ページ続きます。
東洋哲学を読むコツ
なにより、「東洋哲学をしっている自分」をつくりあげてしまって、「まわりがバカ」にみえてきたら、「終わり」です。冷静になりましょう。
東洋哲学にたどりついている時点で、われわれは超こじらせてます。
東洋哲学にくわしいことを、自慢するようになっちゃったら、こじらせすぎて、アウトです。ブッダもおてあげ。完全に僕の話です。ほんとすいません。
東洋哲学は、「楽になるため」にあります。
p351-352
知識を増やすこと、学ぶことに執着してしまうと、言葉にとらわれて、堂々巡りに陥ってしまう。「禅」の達摩大師がそうであったように、ときには言葉を捨て、物事を心で観るということが、大切なのかもしれません。

自分とか、ないから。 教養としての東洋哲学 [ しんめいP ]
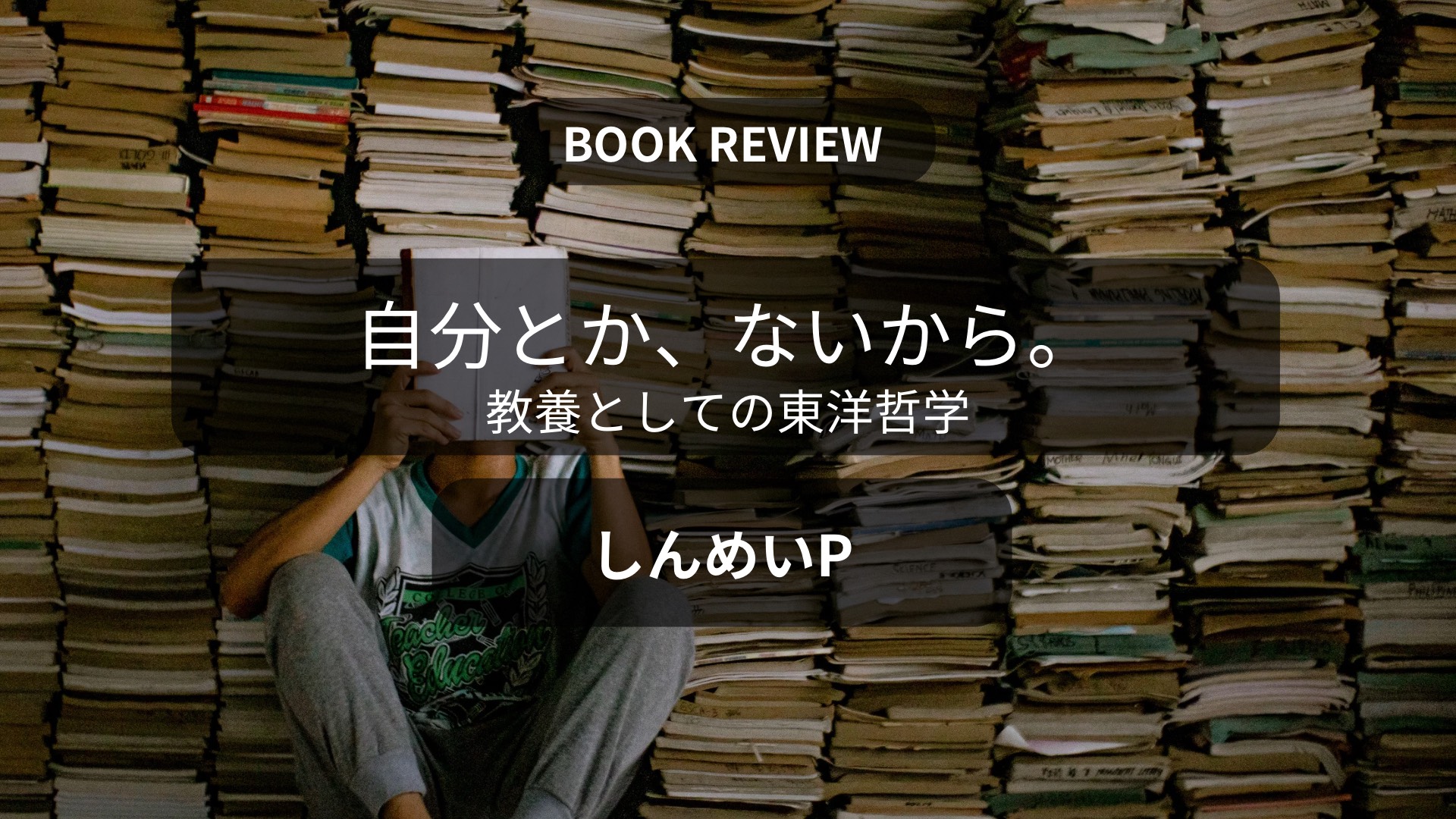
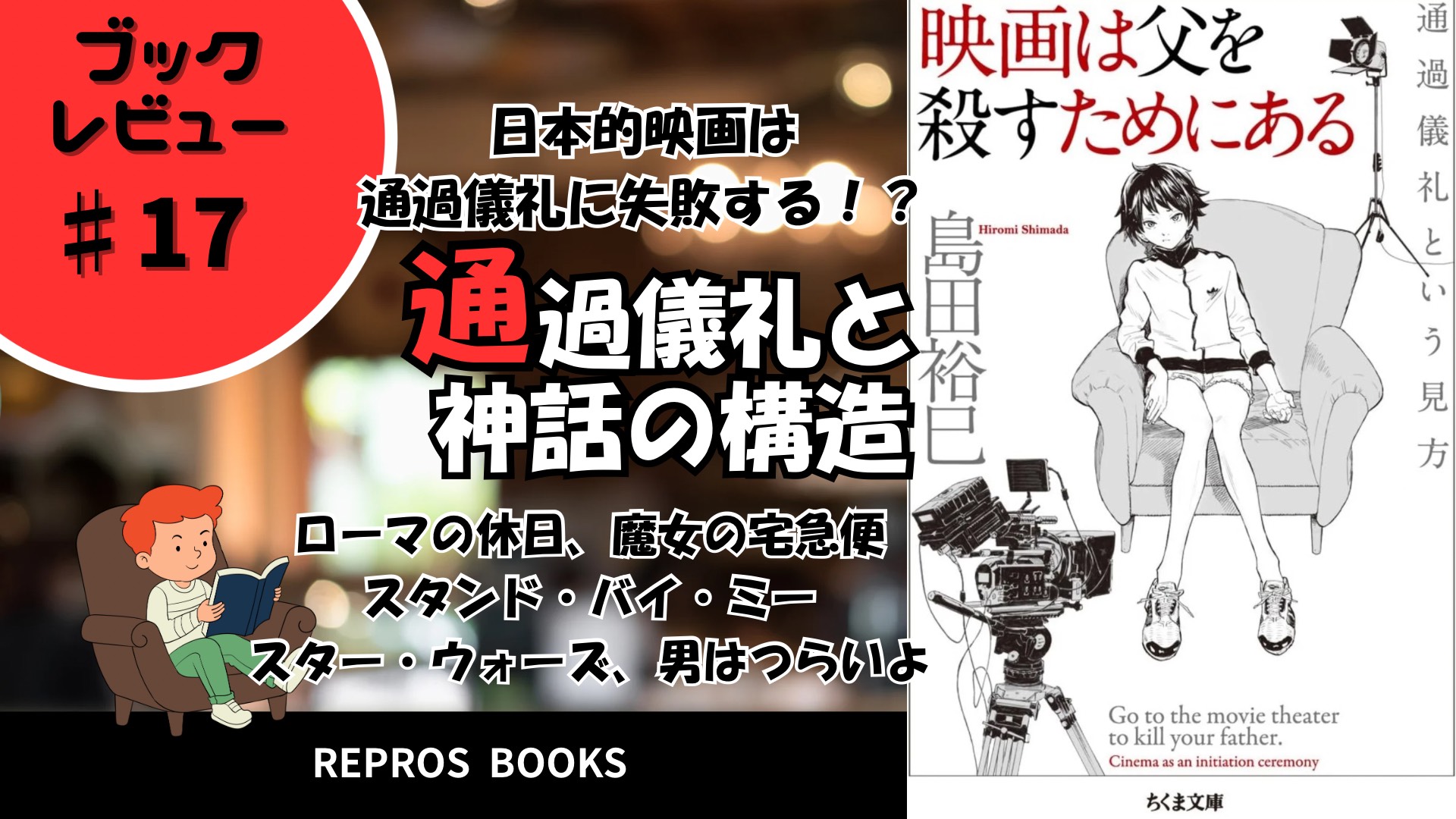
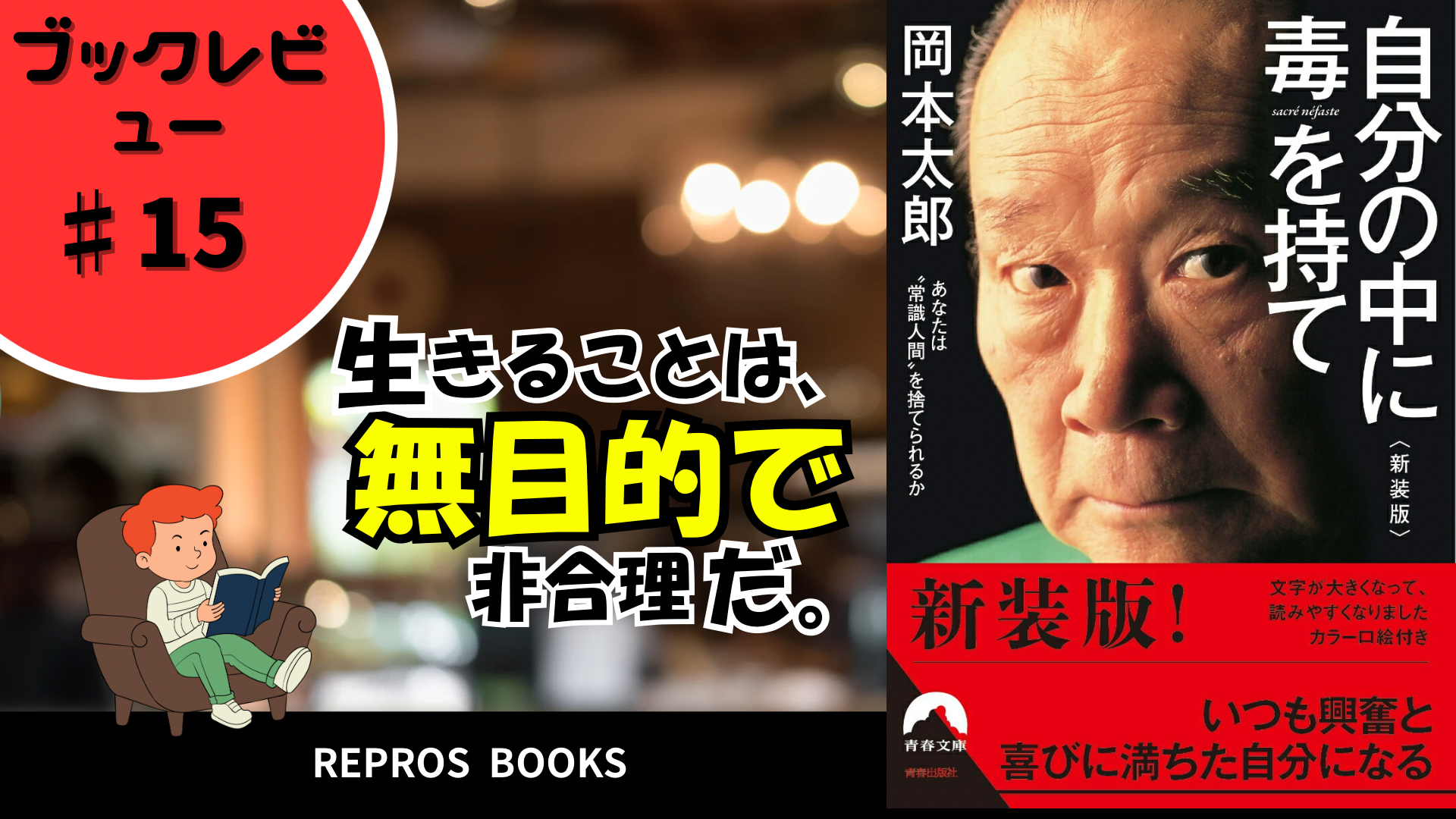
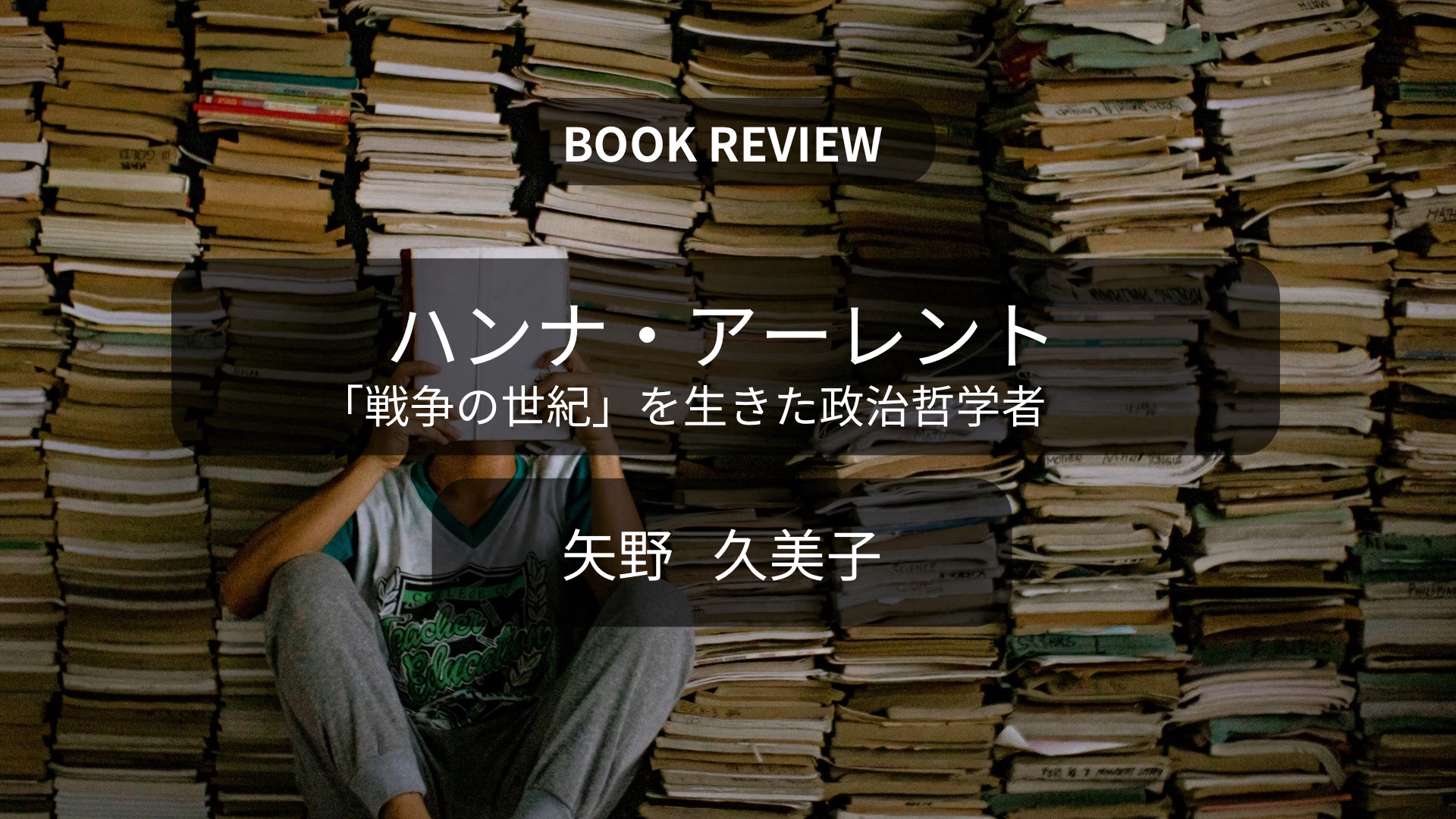
コメントを送信