『彼岸の図書館ーぼくたちの「移住」のかたち』青木真兵・海青子(夕書房)2019年
生命力を高める場「彼岸の図書館」
奈良県東吉野村に移住して「人文学系私設図書館ルチャ・リブロ」という自宅兼図書館を設立した青木真兵さん・海青子さん夫妻の著書になります。本書は、2015年9月から2018年末までの「オムライスラヂオ」というラジオ放送内での対談がベースになっています。
青木夫妻が運営する図書館は、住居スペースと、開放している図書館スペースの明確が区切りがない「住み開き」の形態をとった社会実験のような場所です。
移住の話がメインというより、それぞれ自分に合った生き方、形態を大切にしていこう。という内容です。
都市と田舎の文明史的転換
内田樹 鎌倉時代になっていちばん変わったのは、「田舎」に政治的・経済的・文化的中心が移動したことなんだ。鎌倉仏教や武道や能楽のような、それ以後の日本文化の骨格になるものがそのときに成立する。大拙によれば、平安時代まで日本にあったものはおおかた中国からの「借り物」で、「日本オリジナル」なものではなかった。
それと同じようなことが今起きているんじゃないかとぼくは思うんだ。平安時代が終わって鎌倉時代が始まったときのような、一種の文明史的転換じゃないかな。青木くんが言うように、消費だけをする都市文明から離脱し、自給自足できる、相互支援的な中間共同体が各地に散在するようになってきた。
p35
消費をする場としての都市と、生産する場としての田舎。本書で指摘されているとおり、田舎に移住し、自給自足に近い暮らしや、半農半Xをされている方は多くいます。
しかし、都市の悪い部分を良かれと思ってコピーしてしまうという課題もあります。不釣り合いな制度であったり、組織の形態であったり、のんびりとした田舎の原初的な良さというものを自ら改悪してしまう。いつの間にか、消費のシステムに組み込まれてしまう。そういった問題もありますが、それが政治的・経済的・文化的な発展の萌芽であるという捉え方もできます。
彼岸と此岸
青木 ぼくらはこの図書館を「彼岸の図書館」と呼んでいます。お金とできるだけ距離をとった世界を表現したいんですよね。お金にかかわらない「ルチャ・リブロ」で過ごしたら、また橋を渡って、お金とズブズブの関係にある社会、此岸の世界に戻っていく。こういう二つの次元を行ったり来たりできることの重要性が、今後すごくたいせつになってくるのだと思っています。
p184
実際に青木さんは社会福祉法人で就労支援員として働き、お金はそこで稼ぎ、図書館の運営は、経済活動から切り離されています。対談のなかにもありますが、稼ぐことのなかで自己実現をしない。というのも一つの選択肢として重要なのかもしれません。
アジール(無縁所)としての領域に、できるだけ貨幣を介入させないことで、資本主義経済の流行りを気にすることなく、純粋な活動をすることができます。
生命力、ジョン・スチュアート・ミル
(中略)自分の本性にしたがわないようにしていると、したがうべき本性が自分のなかからなくなる。人間としての能力は衰え、働かなくなる。強い願望も素朴な喜びももてなくなり、自分で育み自分自身のものだといえるような意見も感情ももたない人間となる。
(ミル著、斉藤悦則訳『自由論』光文社古典新訳文庫、二〇一二年、一四八-一四九頁)
p214
19世紀イギリスの思想家ジョン・スチュアート・ミルの言葉を引用し、社会に要請された一つのものさしで物事を測ることが、人間の生命力を弱める。としています。
生命力を高めるためには、「すべての問いを自分に向けること。」、生物種の多さが地球全体の生命力を高めるのと同じように、人間の価値観や生き方の多さや、その多様さが担保される場こそが、人間の生命力を高める、最高で最良の部分が十分活動できる場となり得る。
土着の時代
ポスト近代は土着の時代です。社会でマイナスに語られがちな「不安定」を、「全体」の中にアジャストさせる。このプロセスが「土着」です。そのためにまずは「なんとなく」を復権させ、「全体を視る環境」を整えること。
p279
対立する二者や、不安定な矛盾をそのまま受け入れる。どちらかが正しくて、どちらかが間違いというのではなく、併存させて、その周囲の環境を微調整していく。「全体」というのは、国家、地方自治体、家庭、学校、職場、町内会など、大小関わらず様々なレベルの「全体」が存在します。
政治的・経済的・文化的な発展というのは、そういったいくつもの「全体」がグラデーションのように層を作ることがきっかけとなるのかもしれません。

彼岸の図書館 ぼくたちの「移住」のかたち [ 青木真兵 ]

自由論 (光文社古典新訳文庫) [ ジョン・ステュアート・ミル ]
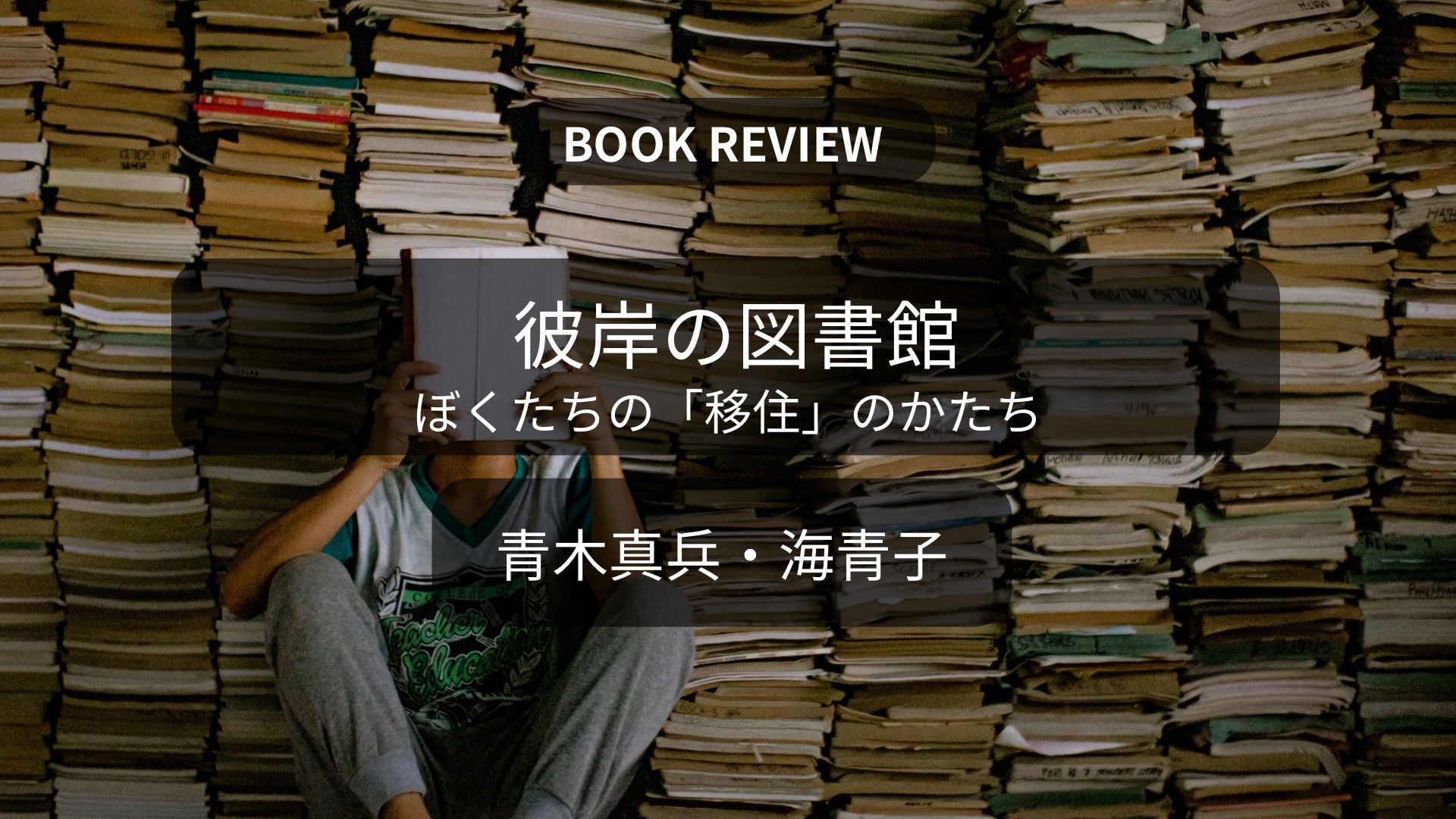
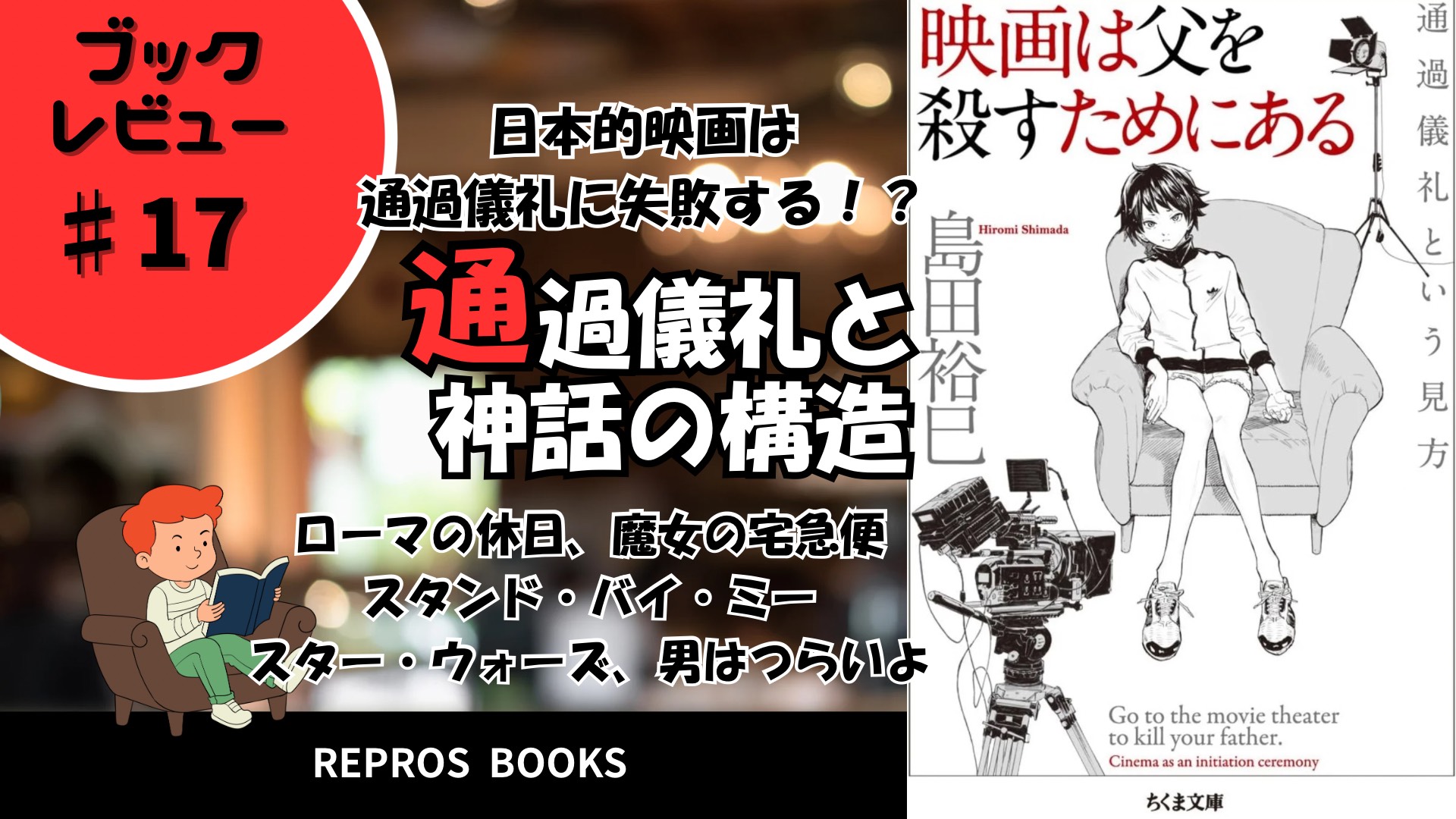
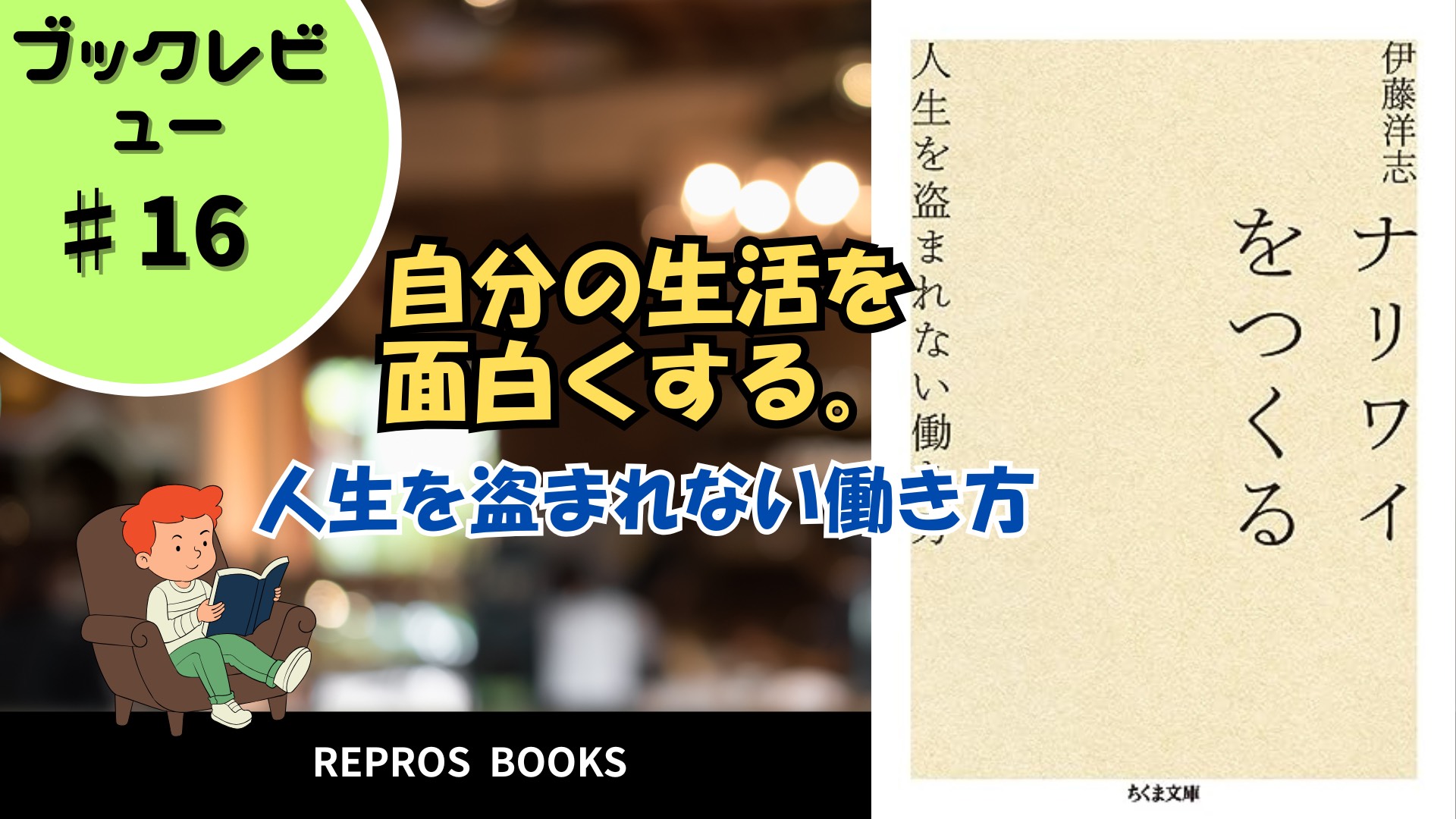
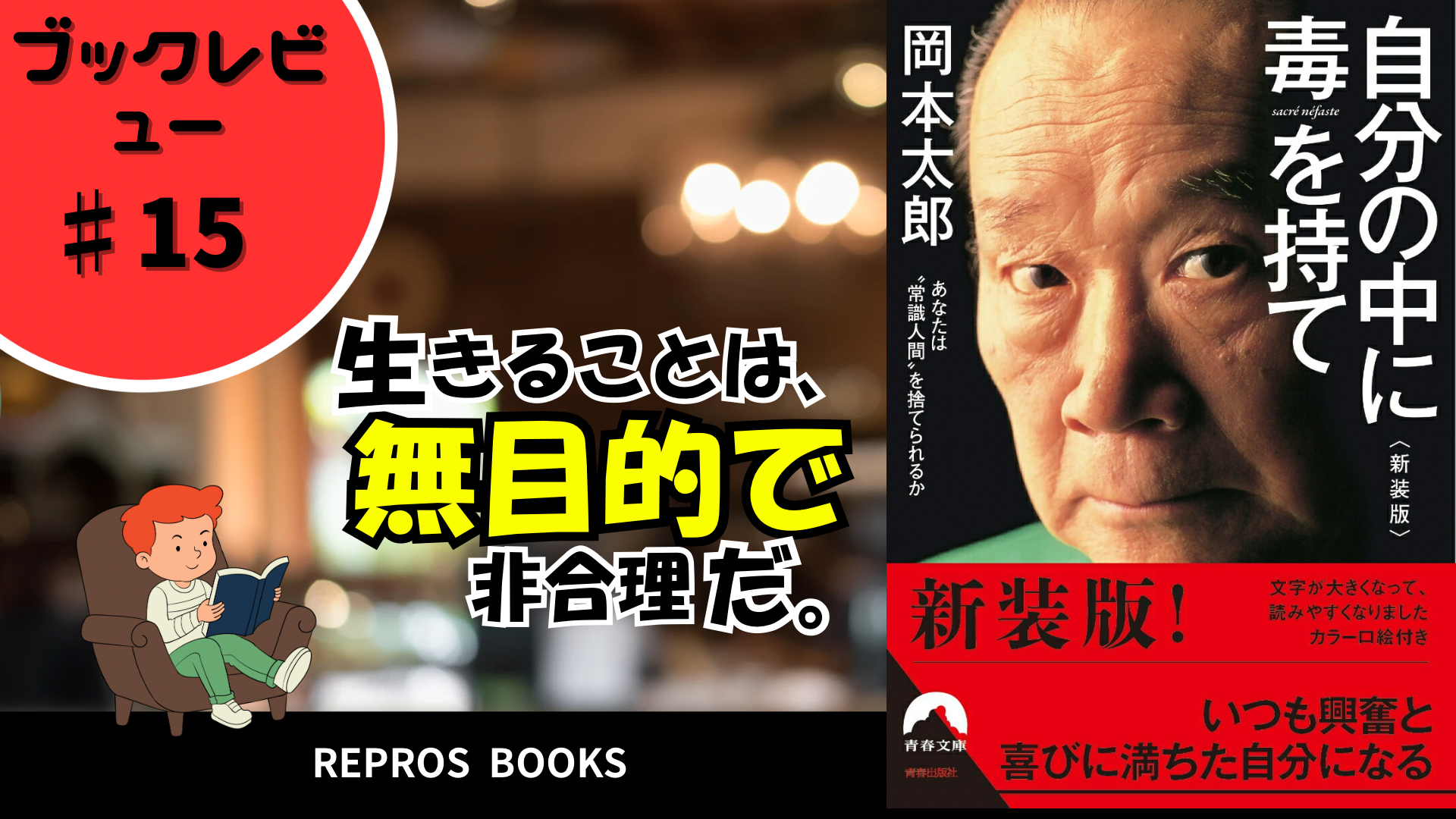
コメントを送信