『ハンナ・アーレント』矢野久美子(中公新書)2014年
命令に「服従」するということは、組織や権威や法律を「支持」すること
ハンナ・アーレントの生涯
ユダヤ人の政治哲学者ハンナ・アーレント(1906‐75)の生涯とその思想を綴った1冊。
アーレントは、大学でハイデガーやヤスパースの元で学び、『全体主義の起源』、『人間の条件』などの思想哲学書を執筆し、後世に多大な影響を与えました。
過激化する前のナチスに一度は逮捕されたものの、1933年ドイツからパリへと亡命し、その後アメリカへと渡ります。
「世界」は、死ぬ存在である個々の人間を超えて持続するものであり、そこに生まれてくる人間は、「始まり」として世界に新しいものを加えうる。しかし、一人ひとりが唯一無二の「誰か」として存在しないかぎりそうした「始まり」はありえない。アーレントはこれらの断片についての考察を『人間の条件』で展開することになる。
p139
「誰かとして存在していない」ことは、同調圧力や全体主義という「砂嵐」のなかで、根こそぎ刈り取られてしまう。ナチス・ドイツの体制下で生きてきたアーレントだからこそ、その危険性について、身を持って自覚し、警鐘を鳴らしています。
人間の条件
1958年に『人間の条件』を刊行しましたが、その背景として、ソビエトの人工衛星スプートニク号の打ち上げ成功による冷戦下の宇宙開発競争や、体外受精による「試験管ベビー」などの影響が考えられるとしています。
中心的テーマは「私たちがおこなっていること」を考えること。
問題は、ただ、私たちが自分の新しい科学的・技術的知識を、この方向に用いることを望むかどうかということであるが、これは科学的手段によっては解決できない。それは第一級の政治的問題であり、したがって職業的科学者や職業的政治屋の決定に委ねることはできない。
(『人間の条件』プロローグ)
p142
労働、仕事、活動
『人間の条件』のなかでも、労働lavor、仕事work、活動actionという、人間の活動力を三種類に区別した部分がもっとも有名で重要です。
【労働】とは、生命を維持するための活動力であり、新陳代謝や消費と密接に結びつく肉体の労働であり、産物としてあとに何も残さない。
【仕事】とは、相対的に耐久性のある物を成果として残す活動力である。芸術作品や詩も仕事の成果としての作品である。
【活動】とは、人と人のあいだでおこなわれる言論や共同の行為であり、絶対に他者を必要とする活動力。自分が「誰であるか」は他者に見られ聞かれるということのなかで現れる。
たとえば、オムレツを作るのは「労働」であり、タイプライターで作品を書くのは「仕事」というような区別です。
現代社会に置き換えて考えると、微妙に重なり合ったり、ずれていたりと解釈が難しいですが、ほとんどの仕事が、労働lavorのみであるといえます。お金のために時間を切り売りし、そのお金も生活の維持費や消費に消えてしまう。ただし、仕事work、活動actionの部分が、インターネットやSNS上での活動だったりと、創作と言論でいえば、近年、活性化しているような気がします。
三種類の区別は、働き方を考えるうえでも非常に参考になります。
公的なもの、私的なもの
アーレントは、大衆社会が耐えがたいのは、人間の数ではなく人びとの世界が「結集させ分離させる力」を失っているからだと述べる。
そうした世界や公的領域のリアリティは、さまざまな物の見方が同時に存在することによってのみ確かなものとなる。「これが公的生活の意味である」とアーレントは言う。どれほど自分の立場が拡大されても、一つの物の見方だけではリアリティは生まれない。「物の周りに集まった人びとが、自分たちは同一のものをまったく多様に見ているということを知っている場合にのみ」世界のリアリティは現れるからである。
p148-149
「私的なこと」というのは奪われていることであるとハーレントはいいます。他者による様々な物の見方や、それに伴うリアリティ。生命そのものよりも、永続的なものを達成する可能性を奪われていること。
公的領域と私的領域の境界が、最も際立っていたのが、古代ギリシアであるとアーレントは指摘しています。ポリスという公的領域では、対等な言論と行為をおこなう自由の領域で、一方でオイコスという家政の私的領域は家長が支配する領域。
しかし、近代では「誰でもない者」による支配、官僚制による「無人支配」によって、公的に共有されていた世界が消滅しているといいます。
SNSの普及している現在では、また一味違った、複雑な支配が誕生しているかもしれません。それは選挙選などに徐々に表れ始めています。
彼女のよれば、一人前の大人が公的生活のなかで命令に「服従」するということは、組織や権威や法律を「支持」することである。「人間という地位に固有の尊厳と名誉」を取り戻すためには、この言葉の違いを考えなければならない。
アーレントは、ナチ政権下で公的な問題を処理していた役人は「歯車」であったかもしれないが法廷で裁かれるのは一人の人間である、と強調し、全体主義の犯罪性の特徴について論じている。
p201
上記の引用は、『責任と判断』に収録されている「独裁体制のもとでの個人の責任」という論文のなかで語られていたことです。命令に「服従」するということは、組織や権威や法律を「支持」することである。非常に厳しい反面、個人の持つ意志や力、自律性に重きを置いた主張であるともいえます。
本書では、あまり思想自体を深堀りして紹介しているわけではないので、ハンナ・アーレントの思想に興味を持った方は『人間の条件』(ちくま学芸文庫)を読むことをおススメします。70年近く前の本ですが、今の日本の現状、働き方、生き方を考えるうえでも十分、プラスになる思想です。
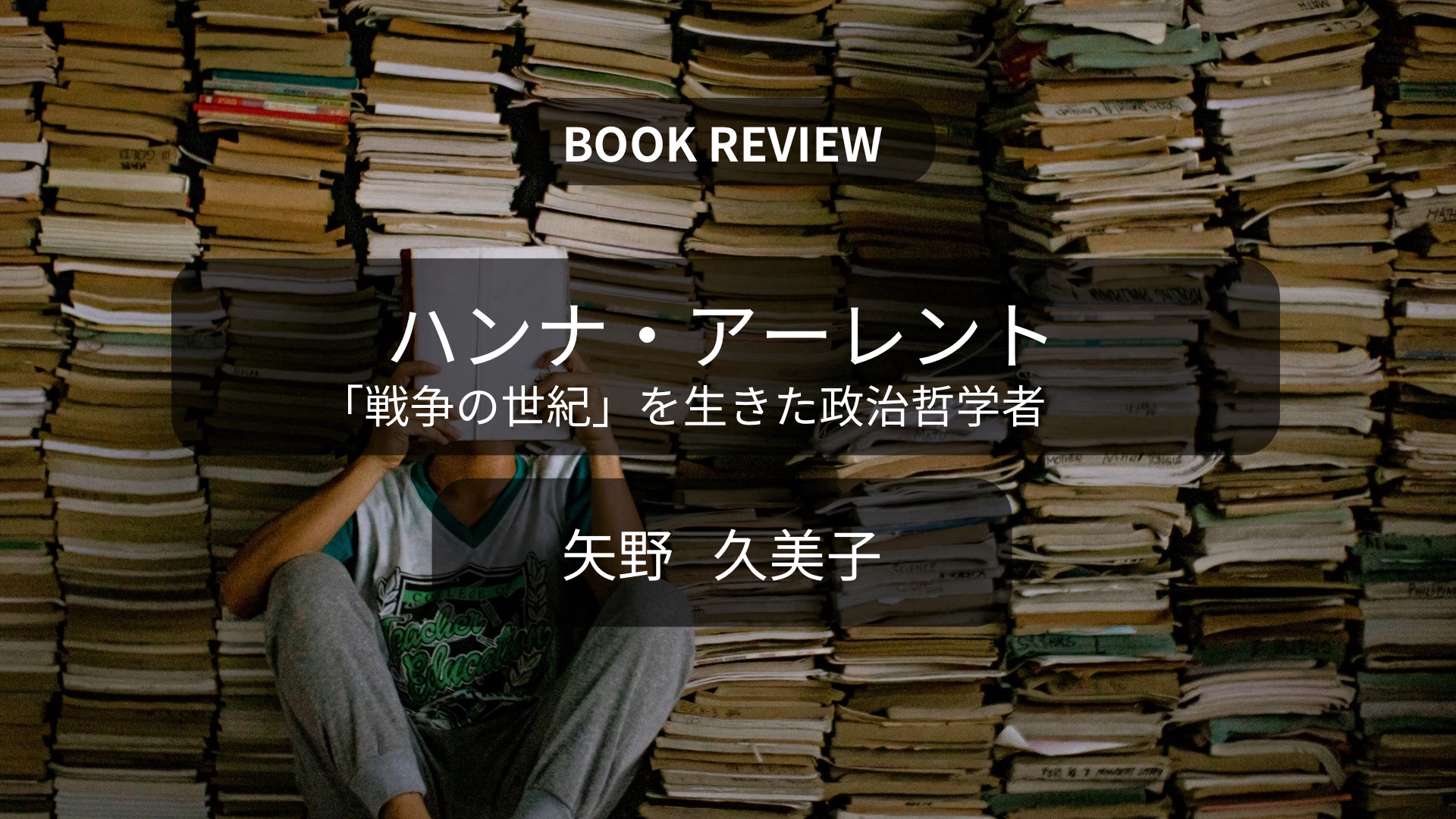
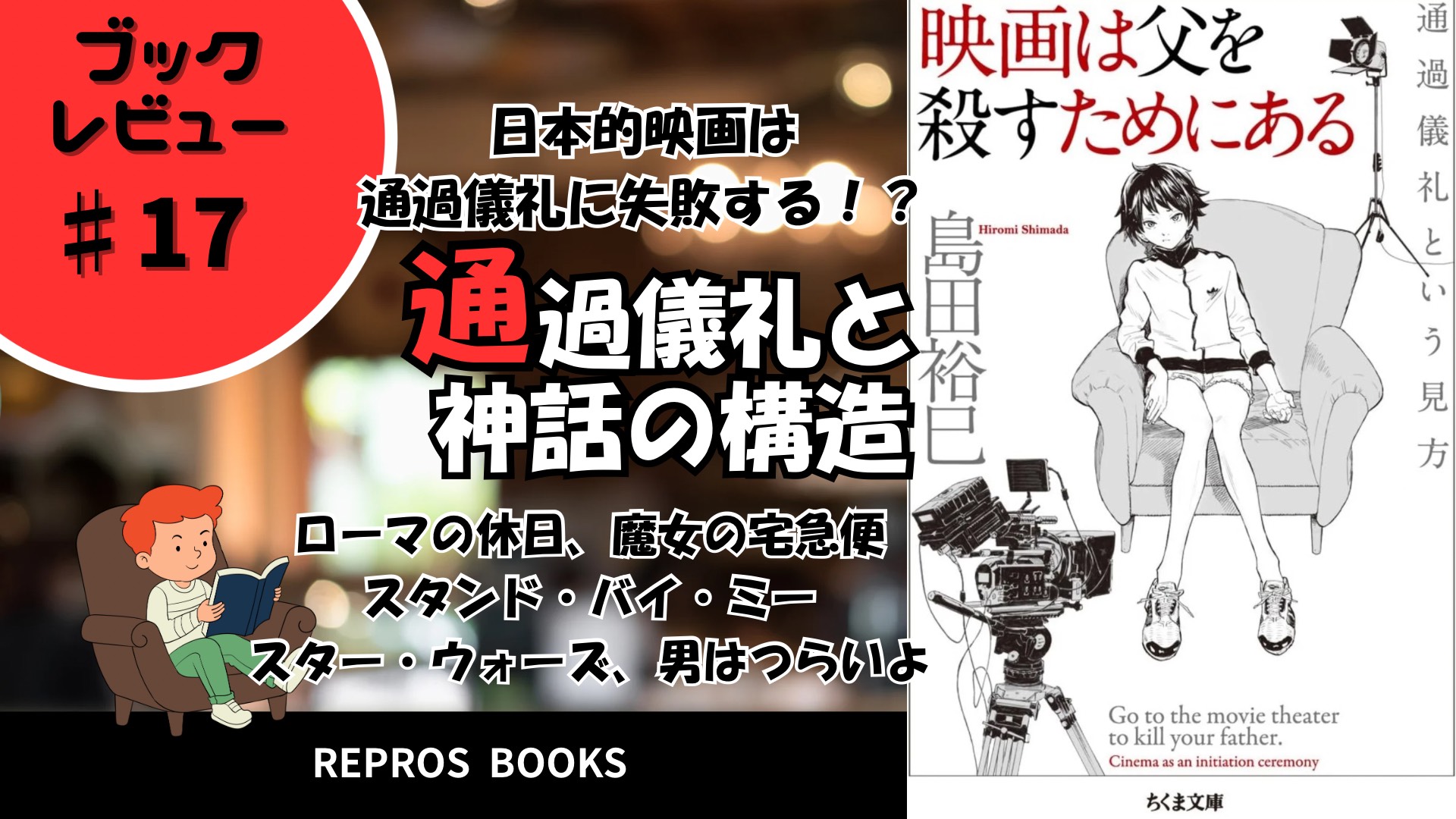
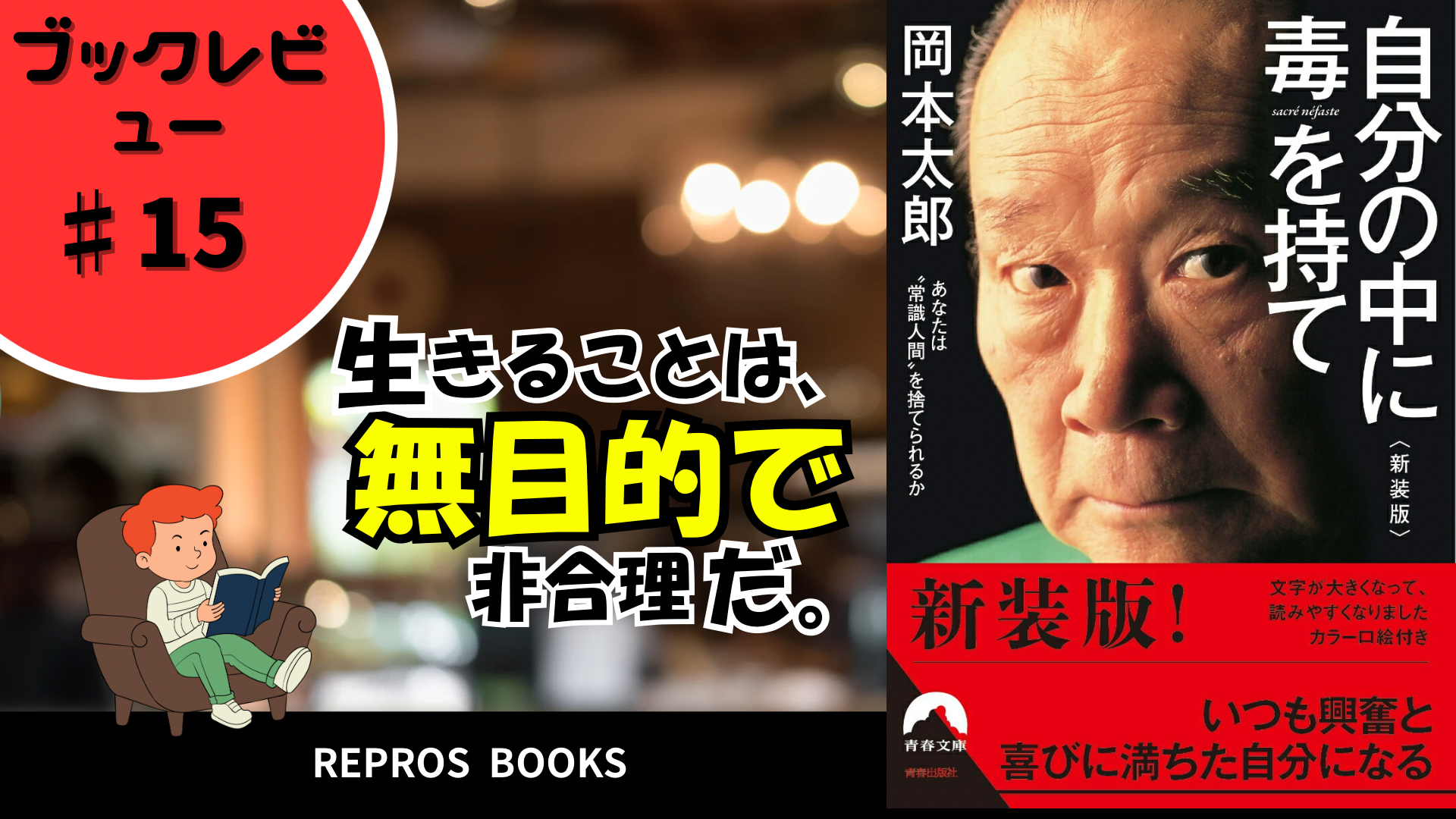
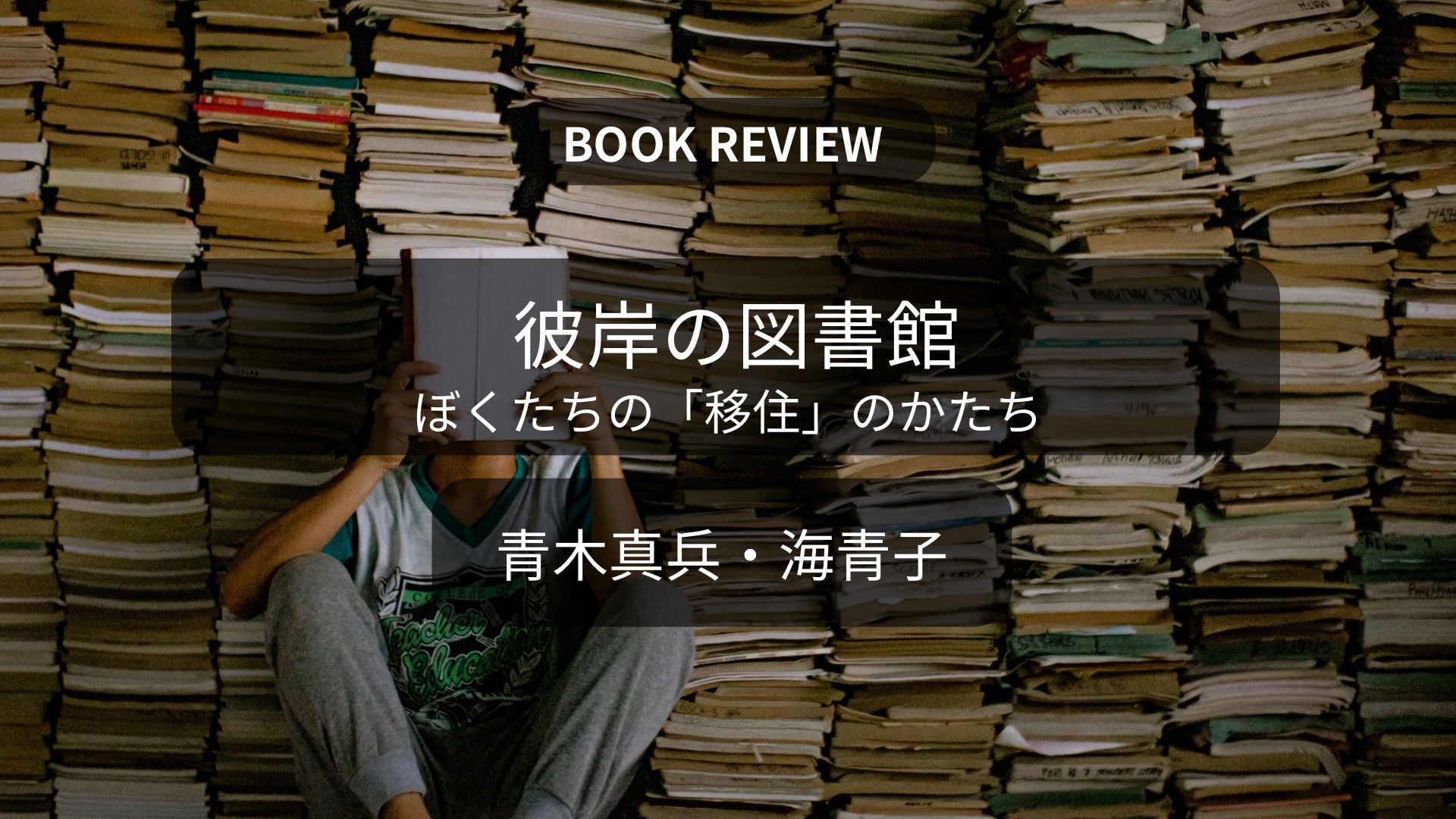
コメントを送信