『人新世の「資本論」』斎藤幸平(集英社新書)2020年
人新世【ひと-しんせい】人類が地球を破壊しつくす時代
カール・マルクス『資本論』
かつて、マルクスは資本主義の辛い現実が引き起こす苦悩を和らげる「宗教」を「大衆のアヘン」だと批判した。SDGsはまさに現代版「大衆のアヘン」である。
アヘンに逃げ込むことなく、直視しなくてはならない現実は、私たち人間が地球のあり方を取り返しのつかないほど大きく変えてしまっているということだ。
人類の経済活動が地球に与えた影響があまりに大きいため、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンは、地質学的に見て、地球は新たな年代に突入したと言い、それを「人新世」(Anthropocene)と名付けた。人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味である。
p4
本書は、経済成長が人類の繁栄の基盤を崩しているという視点から、カール・マルクスの『資本論』などの著作を参照し、地球環境を守りつつ、人間がよりよい社会をつくるにはどうすればいいか。という持論を展開しています。冒頭からいきなりSDGsは現代版「大衆のアヘン」と断定しているところに勢いがあります。
環境負荷
社会学者のシュテファン・レーセニッヒや、イマニュエル・ウォーラーステインの言葉を引用しながら、資本主義においては、資源を周辺部から略奪し、略奪のために生態系をも破壊する。先進国の食料やエネルギーは、どこか遠くの人々や自然環境に負荷を転嫁して、成り立っているとしています。
資本は無限の価値増殖を目指すが、地球は有限である。外部を使いつくすと、今までのやり方はうまくいかなくなる。危機が始まるのだ。これが「人新世」の危機の本質である。
p37
収奪と負荷の外部化、矛盾の転嫁、問題の先送りについては、カール・マルクスが19世紀半ばにすでに分析・指摘していました。
二酸化炭素排出量を減らすなど、デカップリング(切り離し・分離)によって、経済成長しながら、環境負荷を大きくしない取組みもされています。しかしながら、十分な速さで削減するのは困難であるとしています。
グリーン・ニューディールと呼ばれる、再生可能エネルギーや電気自動車を普及さえるための大型財政出動や公共投資でさえも、必然的に環境負荷を増大させることに繋がってしまう。このあたりが、SDGsは大衆のアヘンである。という言葉に回収されていきます。エコな商品を作り出すためにも、資源やエネルギーが使われ、そして廃棄される。SDGsという商品として流通していく。
そうなると、経済成長という道から、脱成長の道を模索するしか方法はありません。
旧来の脱成長
旧来の脱成長論では、単純の資本主義の矛盾の外部化や転嫁、資源の略奪、利益優先の体質を辞めて、労働者や消費者の幸福実現にシフトしようとしたものです。枠組みはそのままで、減速していくイメージです。資本主義でありつつ、その仕組みの内部で脱成長を目指すということです。しかし、著者はそれは不可能であると指摘しています。
日本の「失われた30年」がそうであったように、成長を目指すことが前提の資本主義のままで、成長ができなくなると、企業は存続をかけてより一層、必死に利益を上げようとします。賃金を下げたり、非正規雇用を増やしたり、リストラを敢行したり、あらゆる経費削減をします。その結果、労働環境も悪化し、貧富の差も広がっていきます。
新しい脱成長
〈コモン〉という第三の道
近年進むマルクス再解釈の鍵となる概念のひとつが、〈コモン〉、あるいは〈共〉と呼ばれる考えだ。〈コモン〉とは、社会的に人々に共有され、管理されるべき富のことを指す。二〇世紀の最期の年にアントニオ・ネグリとマイケル・ハートというふたりのマルクス主義者が、共著『〈帝国〉』のなかで、提起して、一躍有名になった概念である。
〈コモン〉は、アメリカ型新自由主義とソ連型国有化の両方に対峙する「第三の道」を切り開く鍵だといっていい。つまり、市場原理主義のように、あらゆるものを商品化するのでもなく、かといって、ソ連型社会主義のようにあらゆるものの国有化を目指すのでもない。第三の道としての〈コモン〉は、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理することを目指す。
p141
本書でも続けて紹介されていますが、日本であれば宇沢弘文氏の『社会的共通資本』が有名です。若干異なる点といえば、「社会的共通資本」は、管理運営がより専門的な人間であるのに対して、「コモン」は、市民が同じような立場で、共同管理することにあります。
水や土壌、自然環境、電力、交通機関といった社会的インフラ、教育や医療といった社会制度。これらを社会的な財産として、国や市場のルールではなく、自分たちで管理することで、持続可能性や社会的平等という課題の解決にも繋がっていきます。共同体のいわば閉じた経済成長しない循環型の定常経済こそ、資本主義とはまったく別の生産原理に基づく脱成長を体現しています。
欠乏性
消費主義社会は、商品が約束する理想が失敗することを織り込むことによってのみ、人々を絶えざる消費に駆り立てることができる。「満たされない」という希少性の感覚こそが、資本主義の原動力なのである。だが、それでは、人々は一向に幸せになれない。
p257
希少であるということが価値を生む仕組みのなかでは、自然環境や新しいライフスタイル、新しい思想さえも商品になってしまいます。新しいものは総じて数が少なく、全体に行きわたっていません。
これは、常に不完全な労働者、不完全な労働力という考え方にも共通しています。我々、人間は生まれつき不完全で学校教育や会社、社会によって、完全に近づいていく。消費社会に取り込まれているうちは、人間さえ商品と同じになってしまいます。
経済成長の前提・根底に欠乏性がある以上、ブランドや希少性、差別化などに捉われないシステムが必要です。
脱成長コミュニズムの柱
それでは具体的にどうしたらいいのか?というところで、第七章では5つの脱成長コミュニズムの柱が提案されています。
①使用価値経済への転換
②労働時間の短縮
③画一的な分業の廃止
④生産過程の民主化
⑤エッセンシャル・ワークの重視
具体的な話も本の中では紹介されていますが、長くなるのでここでは割愛します。重要なのは、物のシェアや再分配、消費の抑制ではく、労働と生産の変革であると著者は指摘しています。
システムの転換には時間がかかりますが、まずは何かをしてみる。アクションを起こしてみる。ということが大切なのかもしれません。賛否両論ある内容ですが、読む方がどういう立場であったとしても、非常に学びのある一冊だと思います。
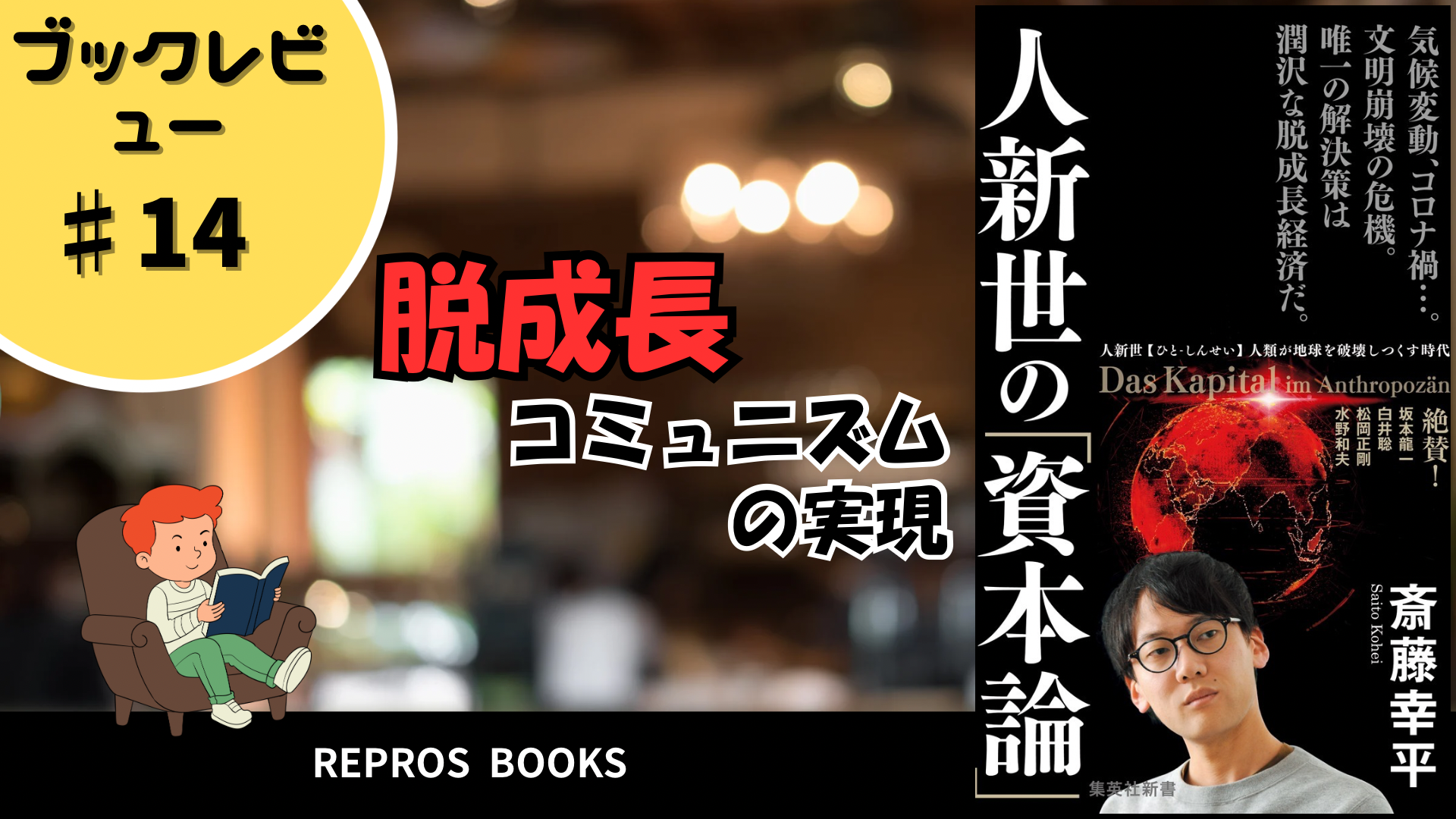
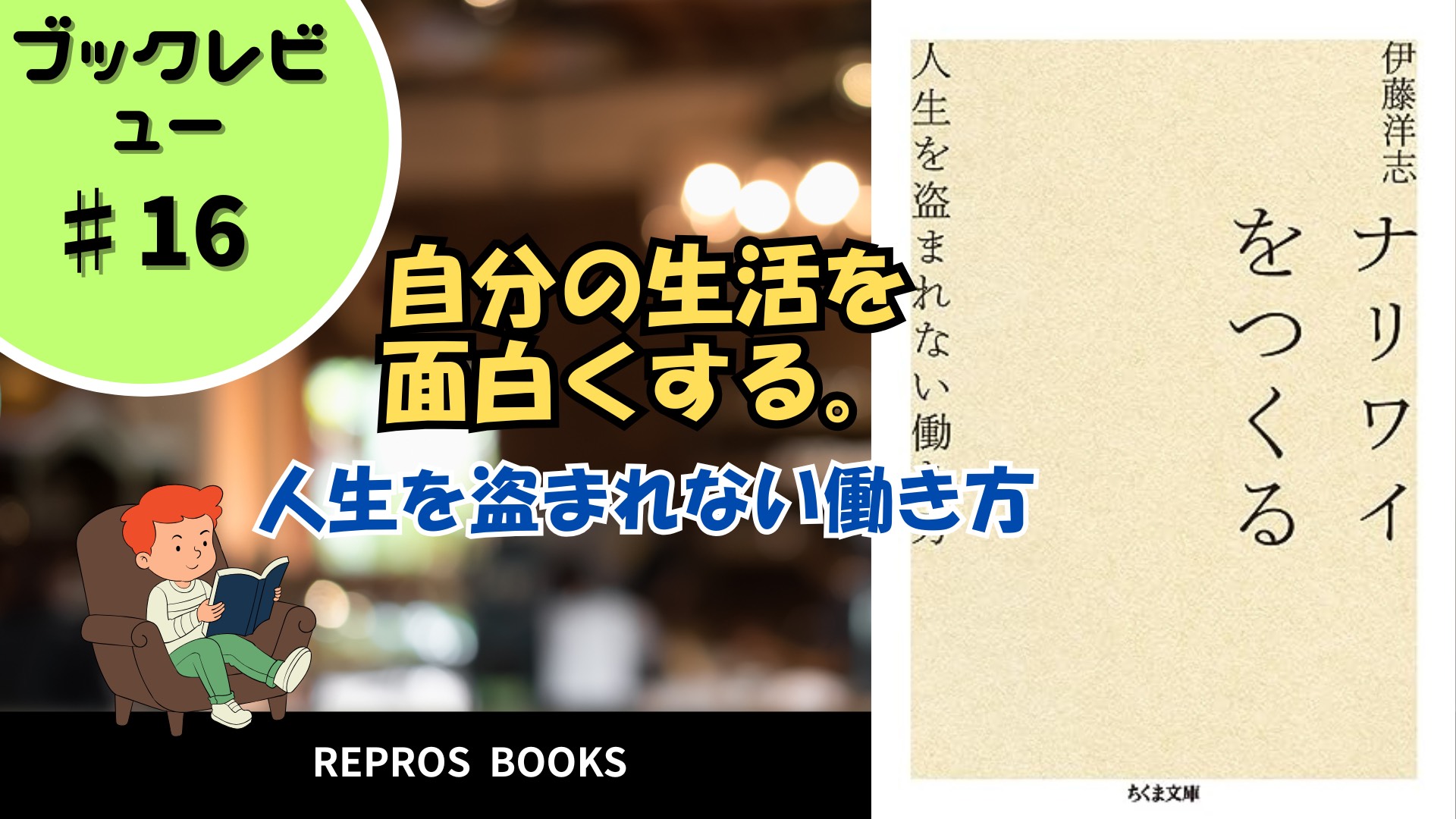
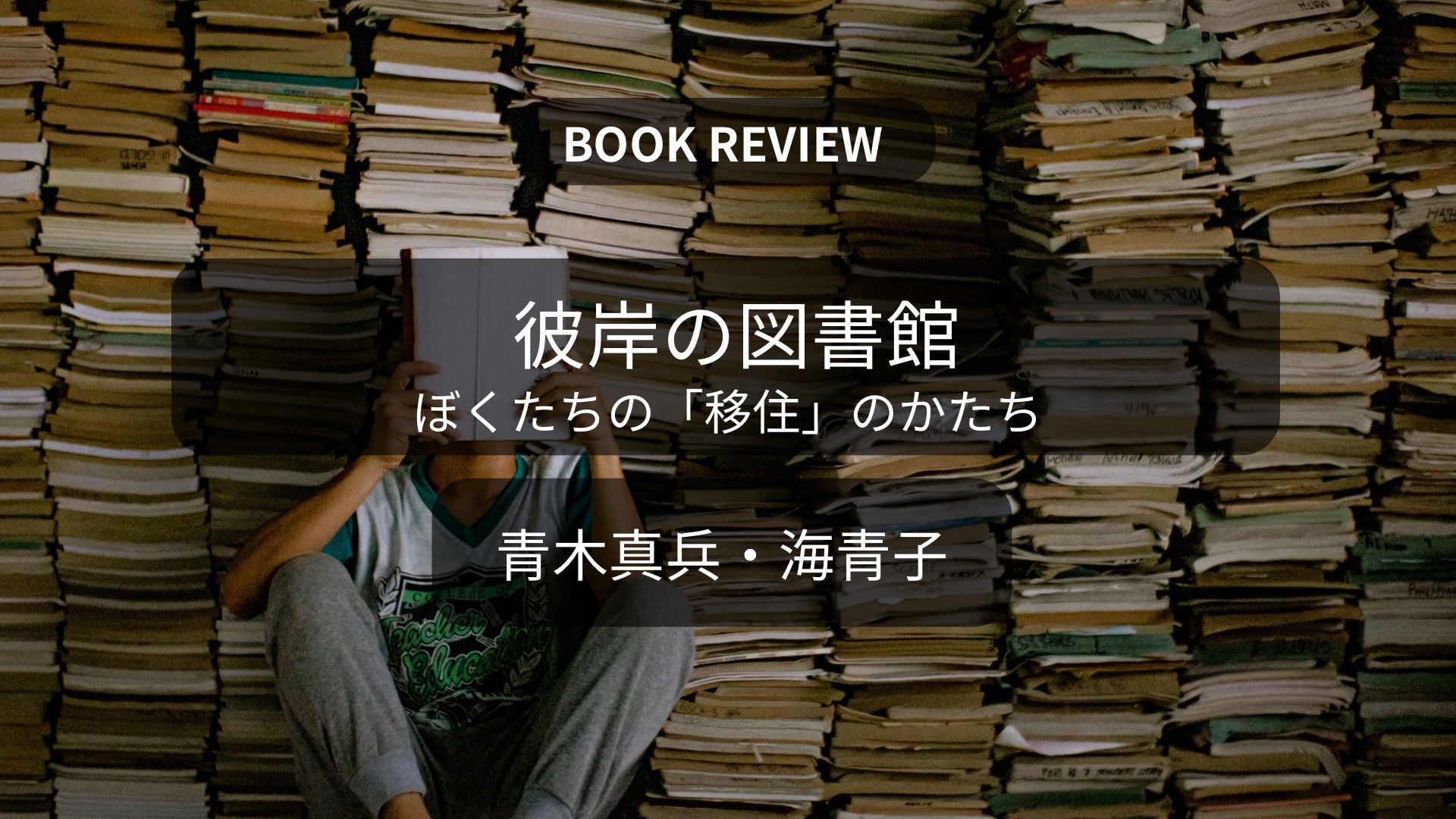
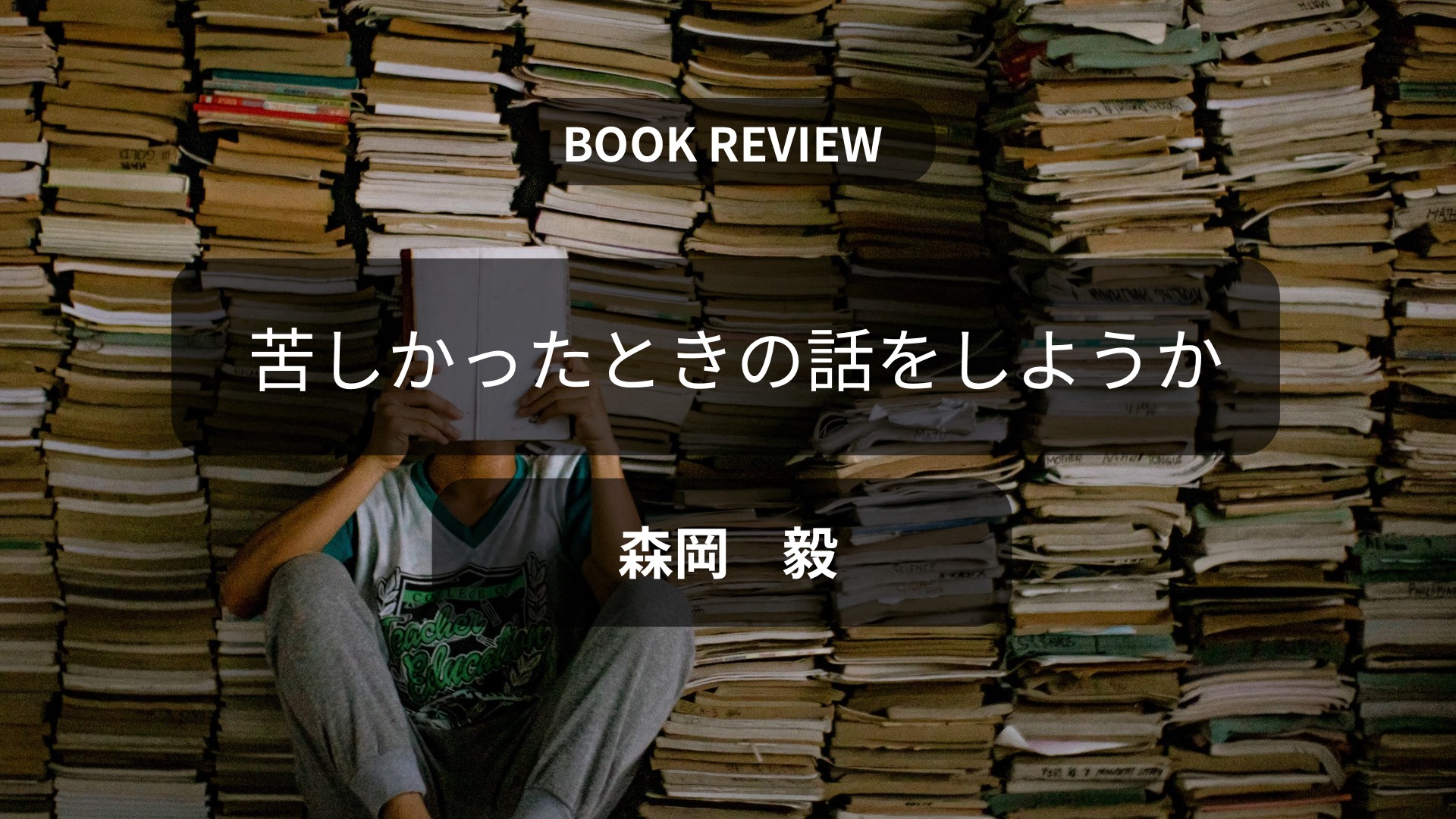
コメントを送信