『自分の中に毒を持て〈新装版〉』岡本太郎(青春文庫)2017年
1960年の大阪万博「太陽の塔」制作で有名な岡本太郎の著書。大阪万博2025(Expo2025大阪・関西万博)の開催が迫っているので、あまり関係ないですが万博つながりで紹介します。本書は、1993年に青春出版社より刊行された本の新装版です。真っ赤なカバーにシンプルな黒文字が非常に目立ちます。毒をイメージしているのでしょうか。格好いいです。
危険な道をゆく
人生は積み重ねだと誰でも思っているようだ。ぼくは逆に、積みへらすべきだと思う。財産も知識も、蓄えれば蓄えるほど、かえって人間は自在さを失ってしまう。過去の蓄積にこだわると、いつの間にか堆積物に埋もれて身動きができなくなる。
p11
18歳でパリにわたった太郎は、そこで「危険な道をとる」覚悟を決めます。1940年、ドイツ軍がフランスを占領する直前にヨーロッパを去り、太平洋戦争突入前夜に日本へ帰ってくるという非常に危険な体験をしますが、日本へ帰ってきてからも、芸術において反体制的な独自の道を歩みます。
端的に言えば、それでは収入は得られない。食えない。つまり生活できないということである。好かれる必要はない。売らないという前提で絵を描き、あらゆる面で権威主義にたてつき、いわば常識を超えて、人の言わないことをあえて言い、挑んだ。
p21-22
他人の目や、自分の目を気にしないで、情熱をかたむけられることをやること。駄目になるつもりのほうがいい。失敗したほうがなお面白いと太郎は語ります。
パリ時代では、全体主義に反対する集会に参加し、そこでマックス・エルンスト、ジョルジュ・バタイユ、アンドレ・ブルトンなどの芸術家と直接、対峙したという事実も、社会の教科書のなかの話のようで興味深いです。
また、本書には記載はないですが、パリ大学では『贈与論』のマルセル・モースに民族学を学んだそうです。そういった錚々たるメンバーに囲まれ、毎日、思考し討論するという環境や、極限状態の社会情勢による鬱積した状況が、太郎の常識に捉われない思想を形成していったのかもしれません。
みんなどうしても、安全な道の方をとりたがるものだけれど、それが駄目なんだ。人間、自分を大切にして、安全を望むんだったら、何もできなくなってしまう。計算づくでない人生を体験することだ。誰もが計算づくて、自分の人生を生きている。
P61
感覚の振り切り方、覚悟の決めた方に関して、面白いのは以下の文章です。
自分をごまかせない人は当然悩む。とりわけピリピリとそれを意識して、辛い。
だが、実は誰でも感じていることじゃないか。
あなたは言葉のもどかしさを感じたことがあるだろうか。とかく、どんなことを言っても、それが自分のほんとうに感じているナマナマしいものとズレているように感じる。たとえ人の前でなく、ひとりごとを言ったとしても、何か作りごとのような気がしてしまう。
これは敏感な人間なら当然感じることだ。
言葉はすべて自分以前にすでに作られたものだし、純粋で、ほんとうの感情はなかなかそれにぴったりあうはずはない。
何を言っても、なんかほんとうの自分じゃないという気がする。自分は創造していない、ほんとうではない、絶えずそういう意識がある。自己嫌悪をおこす。
そんなとき自己嫌悪をのり越えて、自分を救う方法が二つあると思う。まったく自分を無の存在と考えるか、あるいは徹底的にそんな自分自身を対決の相手として、猛烈に闘ってやろうと決めるか、どっちかだ。
どっちでもいい。ただ中途半端は駄目だ。
p96-97
純粋にストレートな表現や生き方を貫いてきたからこそ、「言葉はすべて自分以前にすでに作られたものだし、純粋で、ほんとうの感情はなかなかそれにぴったりあうはずはない。」という言葉がでてきたのだと思います。
あるいは、ソシュールなど構造主義の影響もあるかもしれません。
たしかに、言われてみれば「言葉」は自分が生まれる前から存在し、「言葉」だけではなくて、概念や言葉づかい、口調、文法、どれをとっても、自分が生み出したものは一つもないです。なので、そこにオリジナルの自分自身の内なる表現が、外部世界に発信する手段としてピッタリ合うものがない。という発想に行きつくのは、かなり繊細かつ俯瞰的な感覚です。
だったら自分をちっぽけで小さな人間と思い、振り切ってしまおう。というのが岡本太郎です。
常識を捨てる
生きるーーそれは本来、無目的で、非合理だ。科学主義者には反論されるだろうが、生命力というものは盲目的は爆発であり、人間存在のほとんどと言ってより巨大な部分は非合理である。われわれはこの世になぜ生まれてきて、生きつづけるのか、それ自体を知らない。存在全体、肉体も精神も強烈な混沌である。そしてわれわれの世界、環境もまた無限の迷路だ。
p220
科学主義、合理主義が人間を自然から切り離しまい、人間をむなしいものにしてしまった。本当の芸術の呪力は、無目的であり、無目的だからこそ人間の全体性、生命の絶対感を回復する強烈な目的を持ち、広く伝えることができると太郎は語ります。
そもそも、人間が生まれたこと、生きること自体に意味や目的がないのだから、ほかのことに意味や目的を設定することはナンセンス、というのは当然といえば当然ですね。
近年は特に「わかりやすさ」が重要視されたり、手軽でインスタントに相手に刺さる手法、メリット、デメリットでの二択の判断や、マーケティングが社会的に好まれているように思います。
自分を大事にしようとするから、逆に生きがいを失ってしまうのだ。
己を殺す決意と情熱をもって危険に対面し、生き抜かなければならない。今日の、すべてが虚無化したこの時点でこそ、かつての時代よりも一段と強烈に挑むべきだ。
p245
自分をごまかさず、うまくやろとせず、失敗するつもりでやる。
社会や障害に対し、妥協せず全力で立ち向かいたい。そんなときにポケットにしのばせたい一冊です。
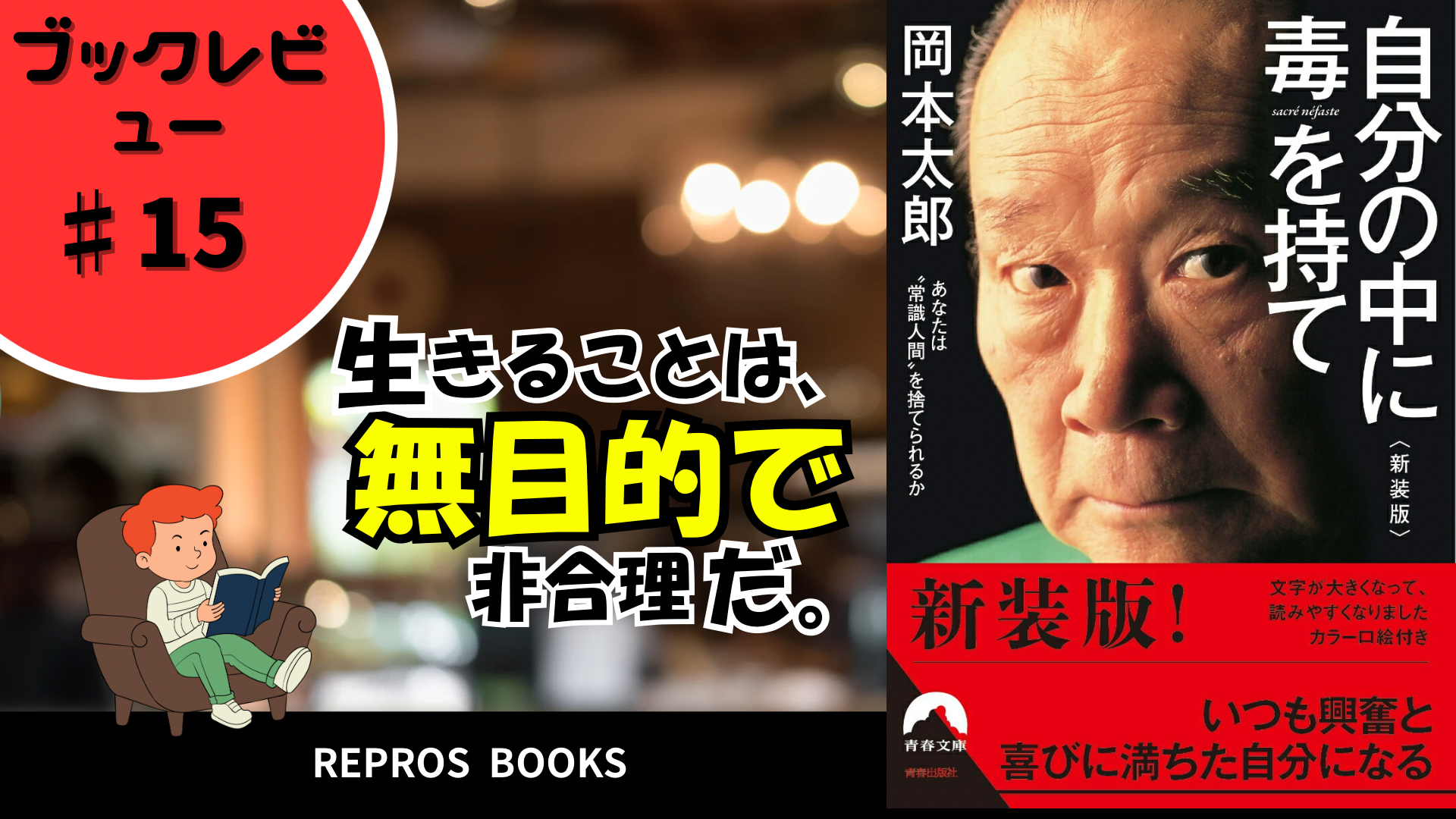
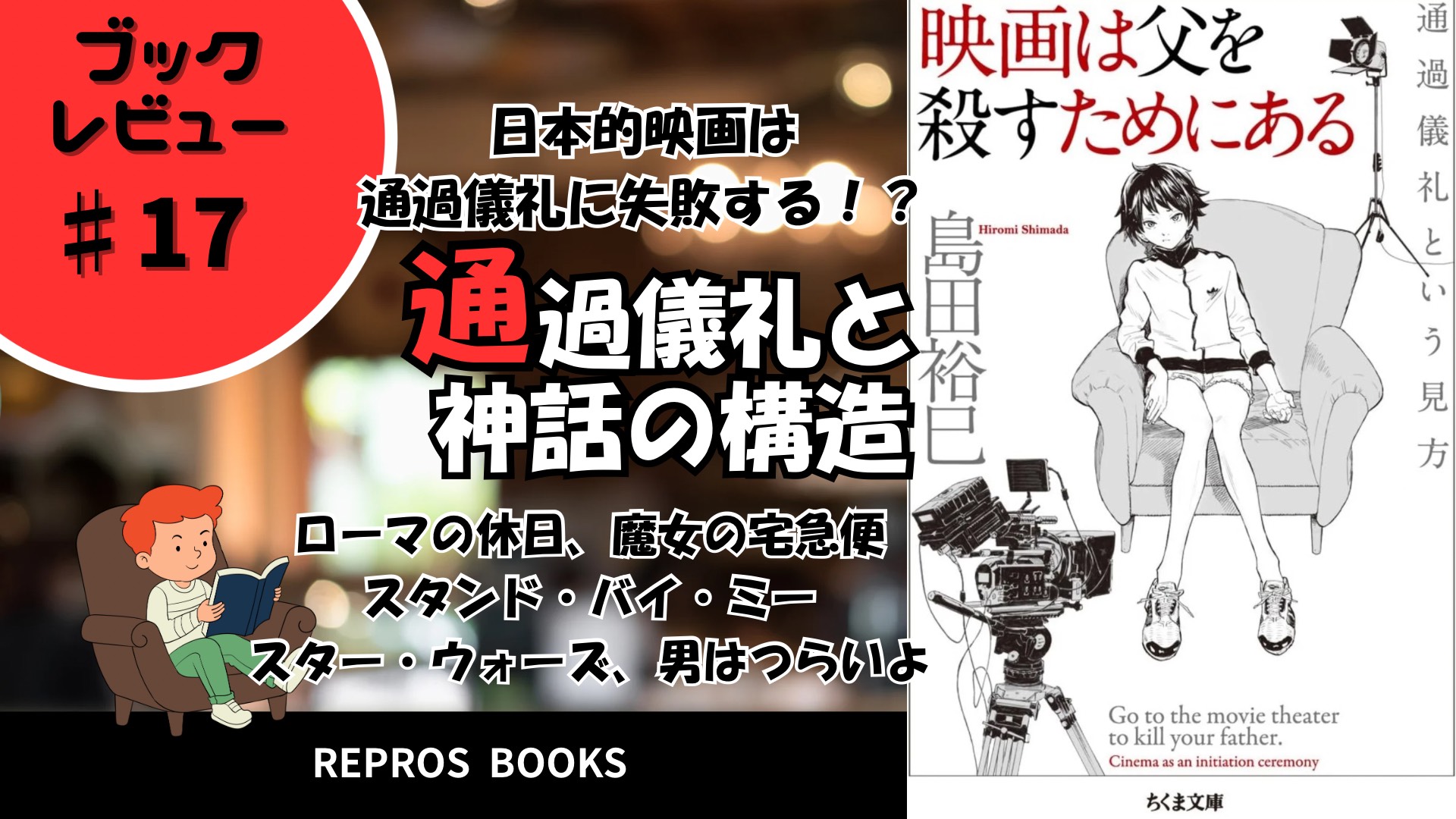
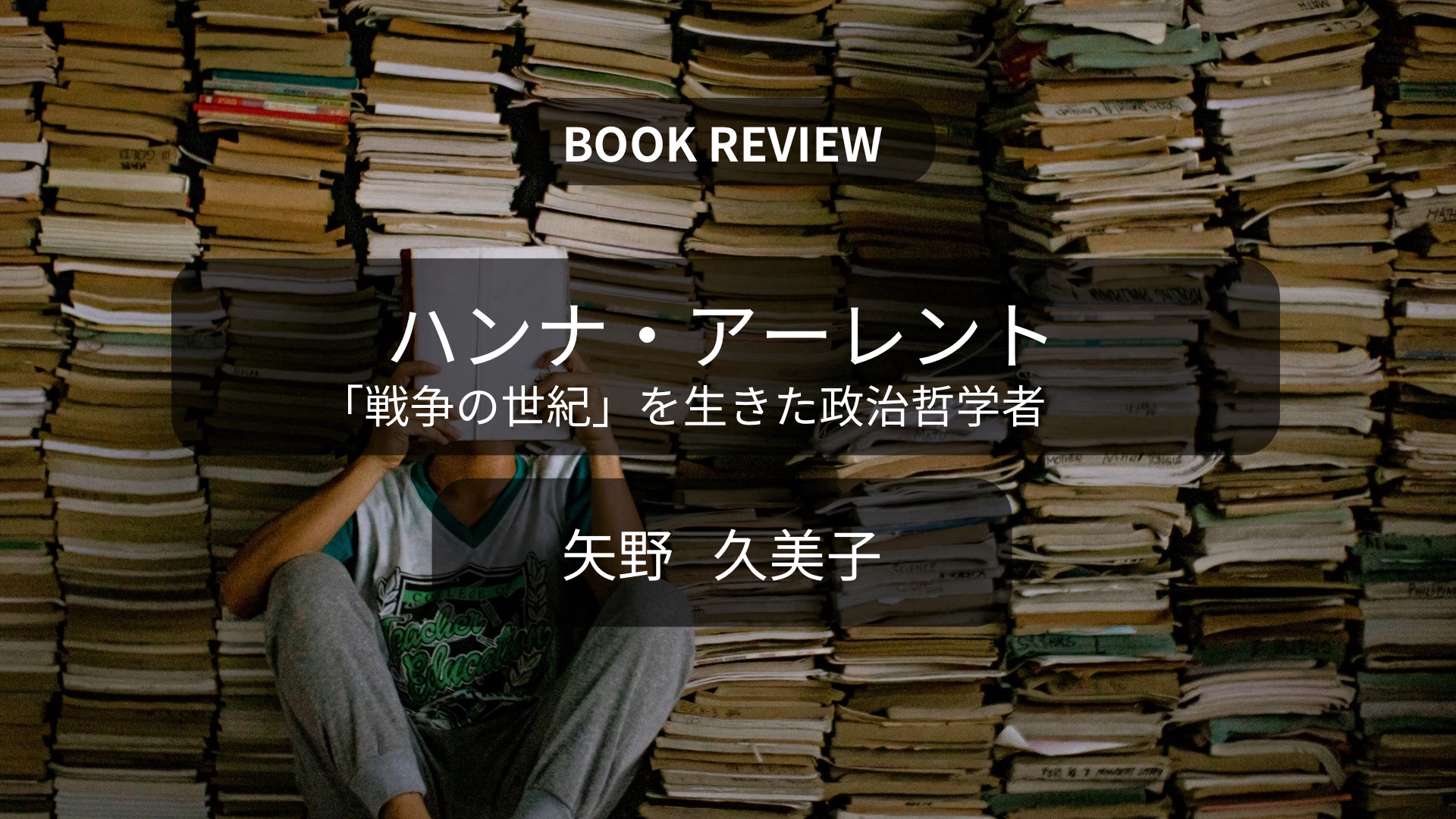
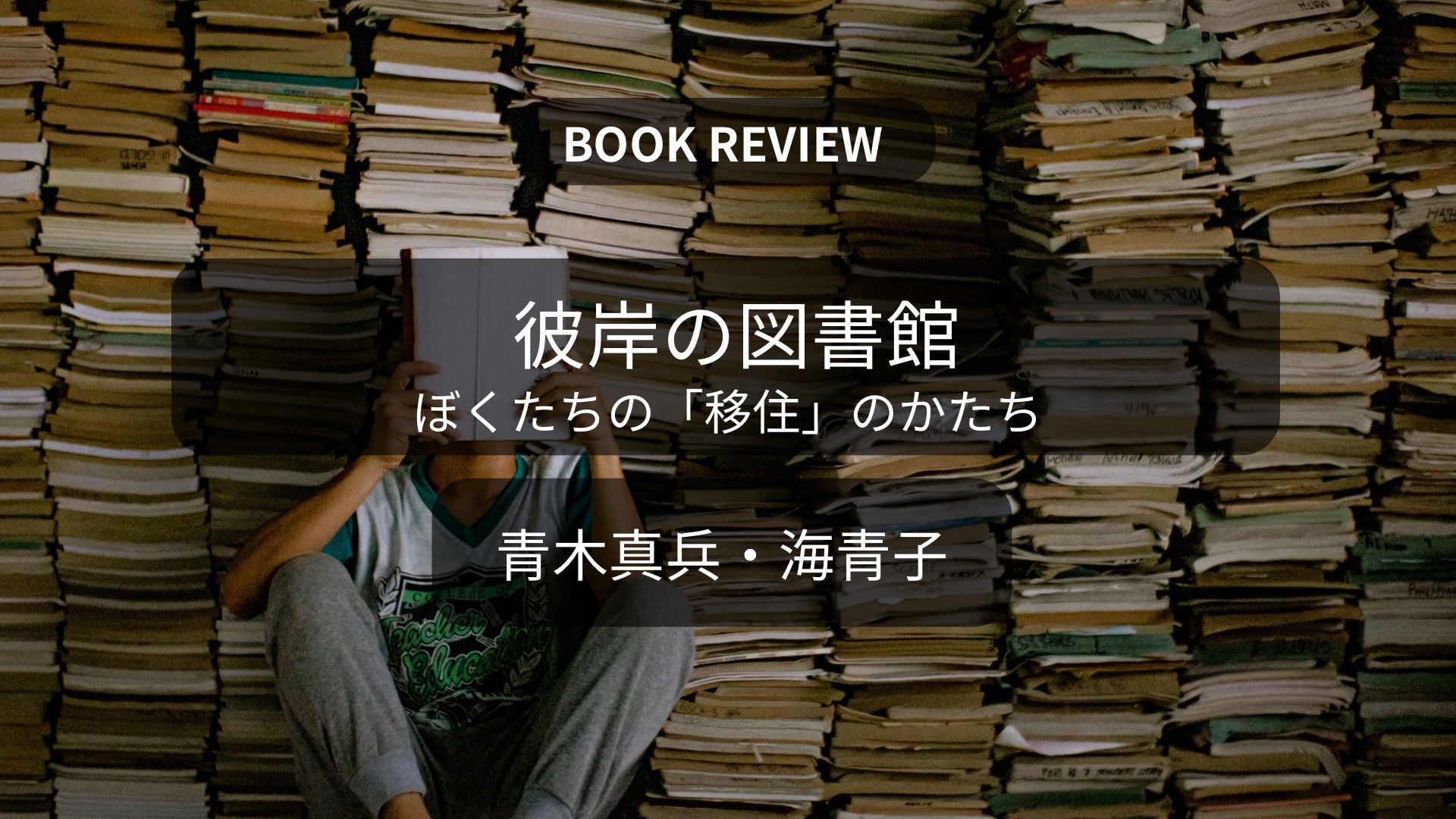
コメントを送信