『ナリワイをつくる』伊藤洋志(ちくま文庫)2017年
本書は2012年に東京書籍から刊行された単行本を増補したものです。
かつては一般的ではなかった会社勤め
自分の時間をお金と交換するのではなく、やればやるほど頭と体が鍛えられ、されに技が身につく仕事を「ナリワイ(生業)」と呼び、実際にご自身でいくつかのナリワイを組み合わせて生活されている伊藤洋志氏による著書です。
大正9年の国勢調査で国民から申告された職業は約3万5000種あり、2011年の厚生労働省の「日本標準職業分類」によれば、2167種。それが、戦後、高度経済成長による急成長によって、職の多様性は失われ、専業化されていきました。(※ちなみに、2022年に日本標準職業分類は改訂され、職業数自体は増えています)
とにかく、戦後になってから、一つの会社にサラリーマンとして雇用されるという働き方が主流になり、季節によって生業を変える、何個も生業を持つという人が極端に減っていったということを示しているようです。
一つの会社に雇用されていれば、自分の生活の時間はほぼ無くなり、そのほとんどを会社に捧げて生きることになりますが、ナリワイによって仕事と生活が一致していれば、その分、生活を自給する能力も高くなり、無駄にお金を使わないので、時間や生活に余裕が生まれてくるといいます。
ナリワイとは
ナリワイの考え方としては、年に1回30万円の仕事や、毎月3万円や5万円などの仕事を同時に何個も持って、生活を組み立てて行こうという、地道なやり方です。
ナリワイの考え方の真髄の一つは、稼がなきゃ稼がなきゃと外部の環境に振り回されるより、自分の生活をつくる能力を磨き、それをちょっと仕事にしてしまうほうが確実ではないか、ということなのである。
p37
100の仕事を持つという意味の百姓という言葉があるように、もともと大多数の日本人は一つの仕事じゃなくて複数の仕事を持っていた。村では、農業はもちろん、石垣をつくれる石屋、藍染をする紺屋、大工、陶工、野鍛冶屋など、多様な仕事を各自が受け持っていたし、春だけ養蜂をやる、冬は藁細工をつくる、杜氏になって酒蔵に出稼ぎする、といった具合に、一人がいくつもの仕事を持つことは当たり前のことだった。
p37・38
世の中は矛盾だらけで、何か矛盾がある以上、それを解決することを行えば仕事になります。現代社会の矛盾がナリワイのネタを探す場所であり、事業やサービスが一見、健全にみえるところであっても、提供側の労働環境は劣悪なケースもあるため、そういった視点を持つことでも、ナリワイを探すことができます。
最近の企業でいうと、雇用と採用のミスマッチによる退職、ブラック企業による退職阻止に対する「退職代行モームリ」や、スキマバイトの「タイミー」なんかが有名ですが、もっと小さい規模なら尚更、普段の生活や暮らしに近いところにヒントが隠されています。
また、ナリワイといったら、フリーランスを思い浮かべるが、クライアントワークは激烈競争に巻き込まれるので、バトルタイプでない人、気力体力が限界を迎える30代後半を迎える人にはお勧めしない。決してナリワイ=クライアントワークではない。と著者はいいます。
ナリワイ10か条
・やると自分の生活が充実する。
・お客さんをサービスに依存させない。
・自力で考え、生活をつくれる人を増やす。
・個人ではじめられる。
・家賃などの固定費に追われないほうがよい。
・提供する人、される人が仲良くなれる。
・専業じゃないことで、専業より本質的なことができる。
・実感が持てる。
・頑張って売上を増やさない。
・自分自身が熱望するものをつくる。
こういったナリワイの要素と、それを導き出した思考の流れも重要になってくるので、さらに各自で付け足していったりして、自分なりの「ナリワイ10か条」を作成することで、目指す暮らしが明確になっていきます。
ライフワークとライスワーク
いっぽう、ランニングコストのためのいわゆる「ライスワーク」で稼いで、理想の仕事を「ライフワーク」で行うというのは、一見現実的に見えるが、それは甘い。ライスワークも仕事のうちだから、自分の感覚に染み付く。その影響は大きい。ライスワークだとたかをくくってやっている感覚が染み付いて、自分の理想の仕事をする感覚を鈍らせる。
p90・91
会社員をしながら安定収入を得て、自分が本当にやりたいこをやる、という作戦も、会社の仕事に対して前向きなのものでなければ、会社の仕事のあとに本来やりたいと思っていたライフワークもいいものになるはずがないのである。
p91
ライスワークなどという、本来やりたいことのためにお金を稼ぐことだけを考えてやる仕事、という後ろ向きな捉え方で仕事をしない方がよい。仕事に対する意識が安易になっていって、つまらない人間になってしまう。これは注意したい。現代社会には、感覚を鈍磨させる罠がたくさんある。
p93
日々の感覚や環境、言葉遣いというのは、ものすごく自分自身の思考に影響を与えるものなので、ここは気をつけなければならないと著者は指摘します。
たしかに、『この仕事はお金稼ぎのため、生活のために仕方なくやっていて、本当にやりたいことは別である。』というスタンスであれば、その考え方は行動に透けて見えてきます。
身の回りの人たちの力を借り、そして身の回りの人たちが困っていることをナリワイとしてお裾分けする。仕事を自給しながら、同時に生活もデザインしていく。新たな視点に立つことができる一冊です。
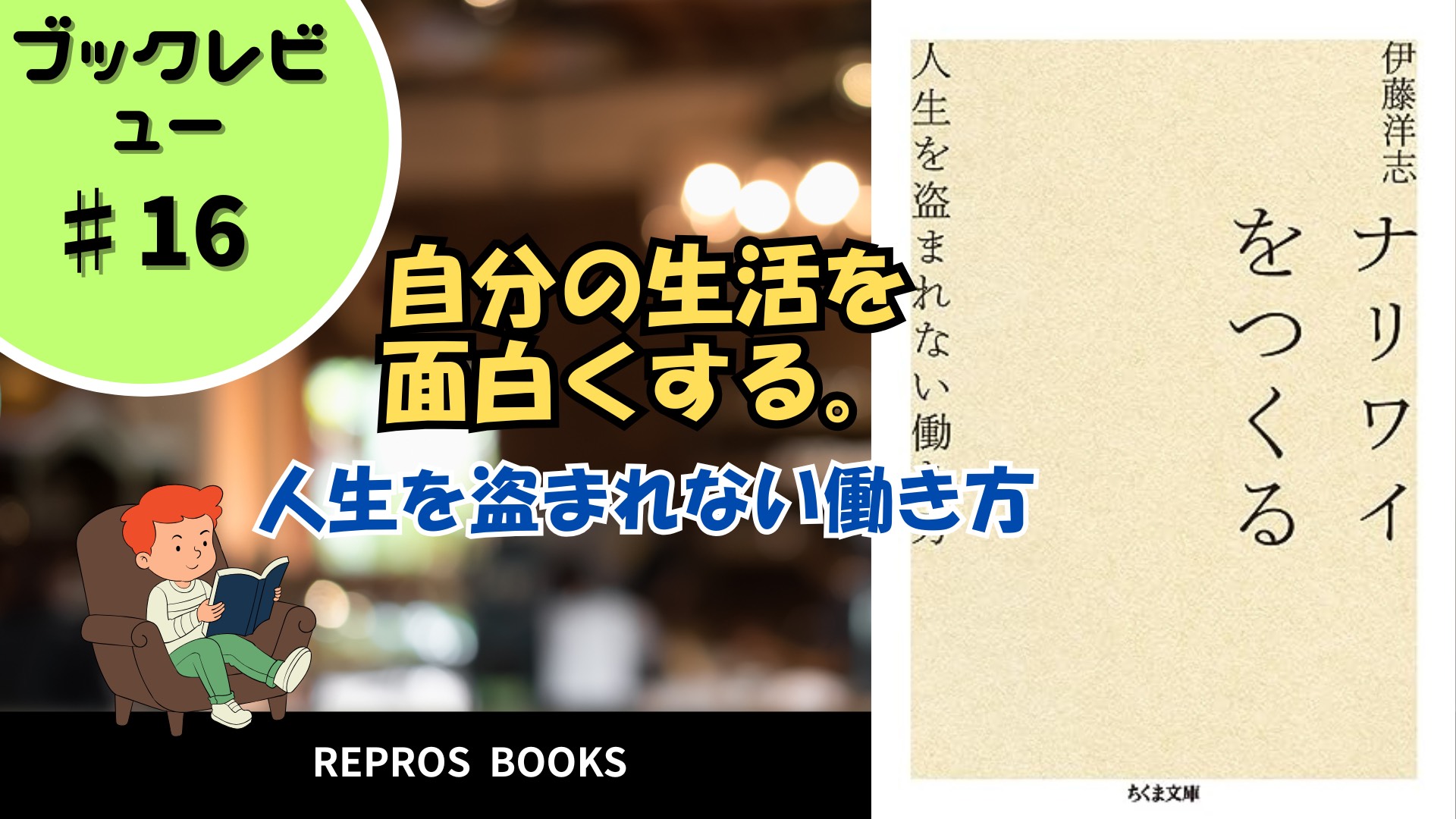
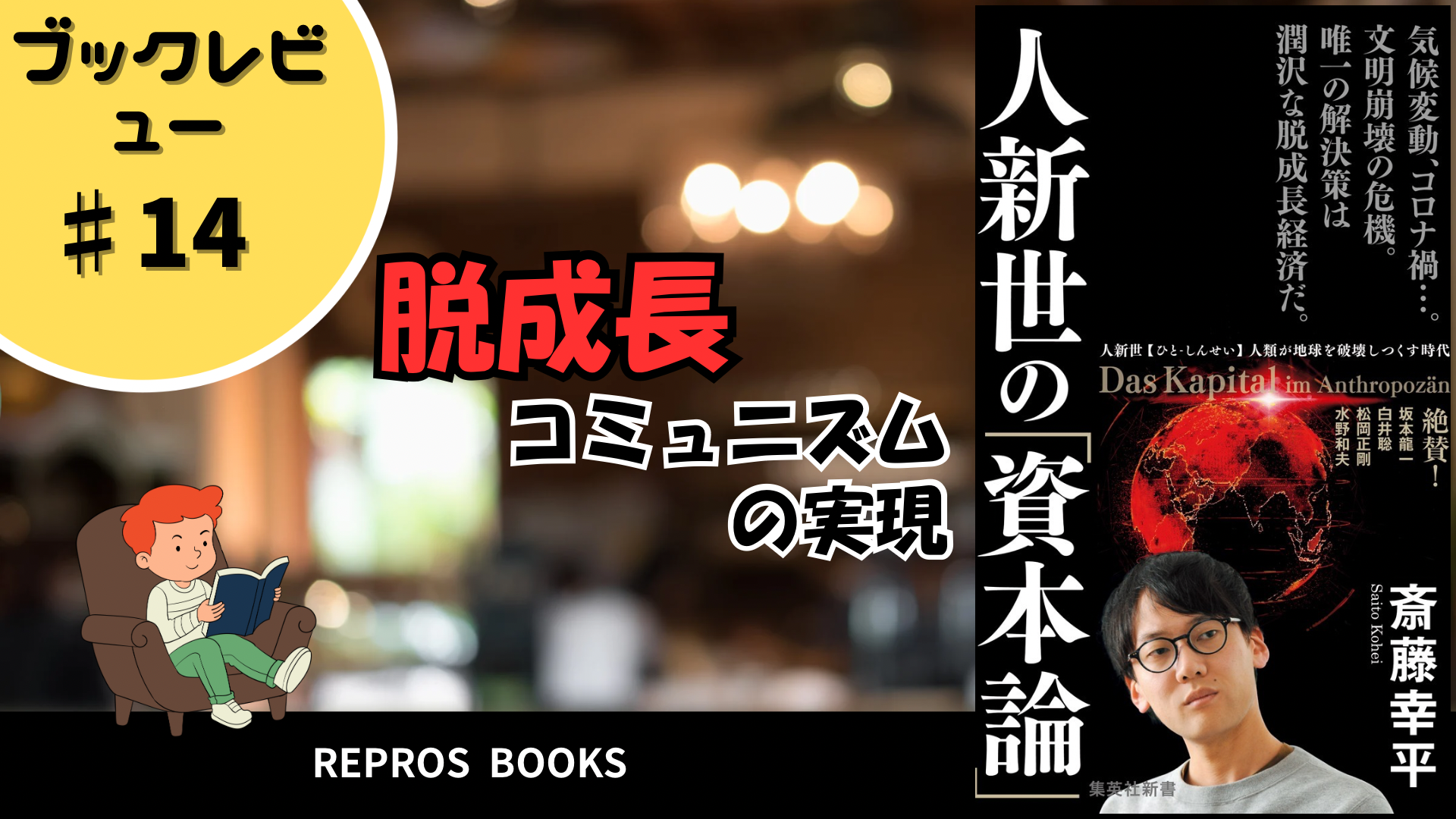
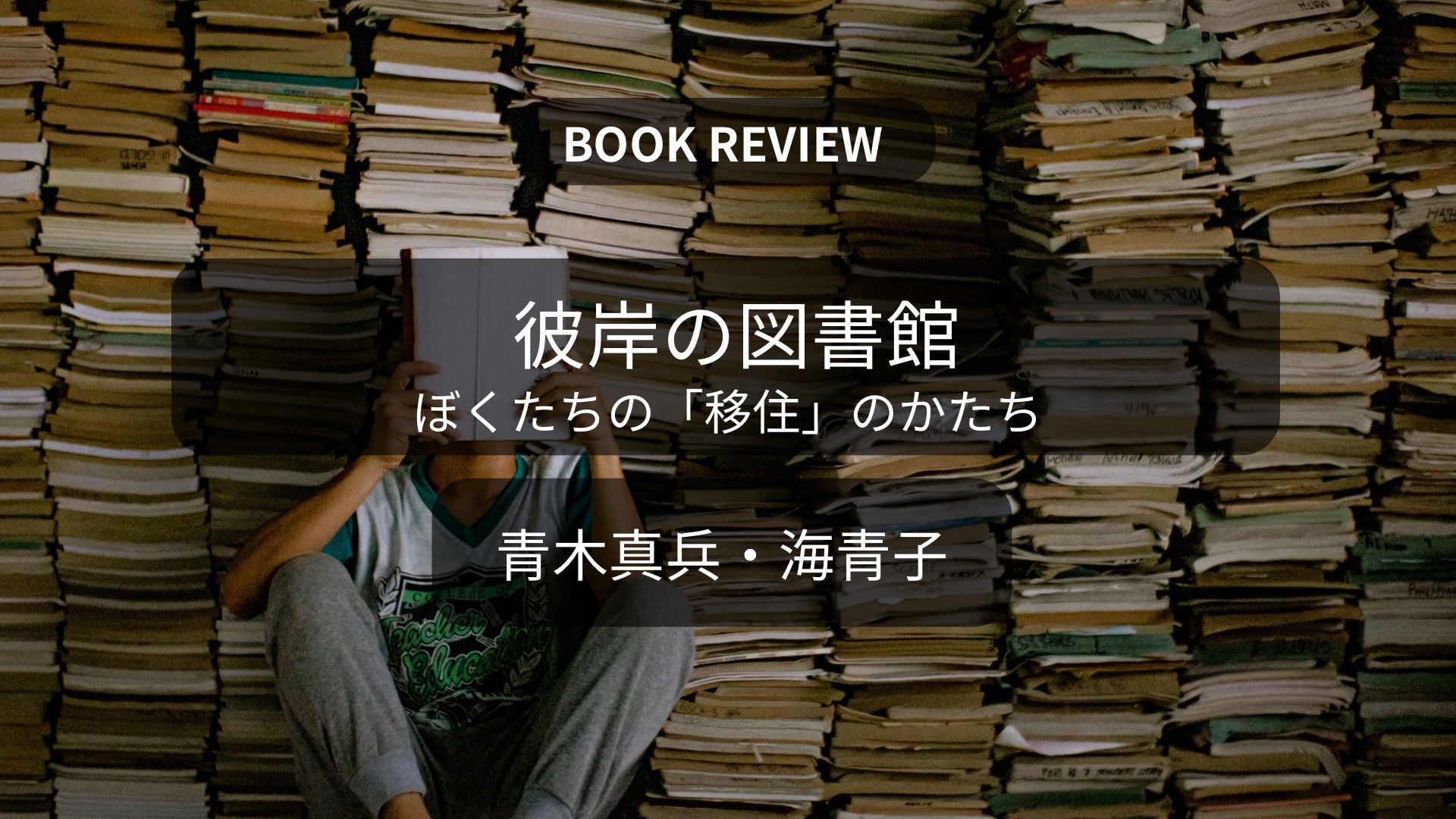
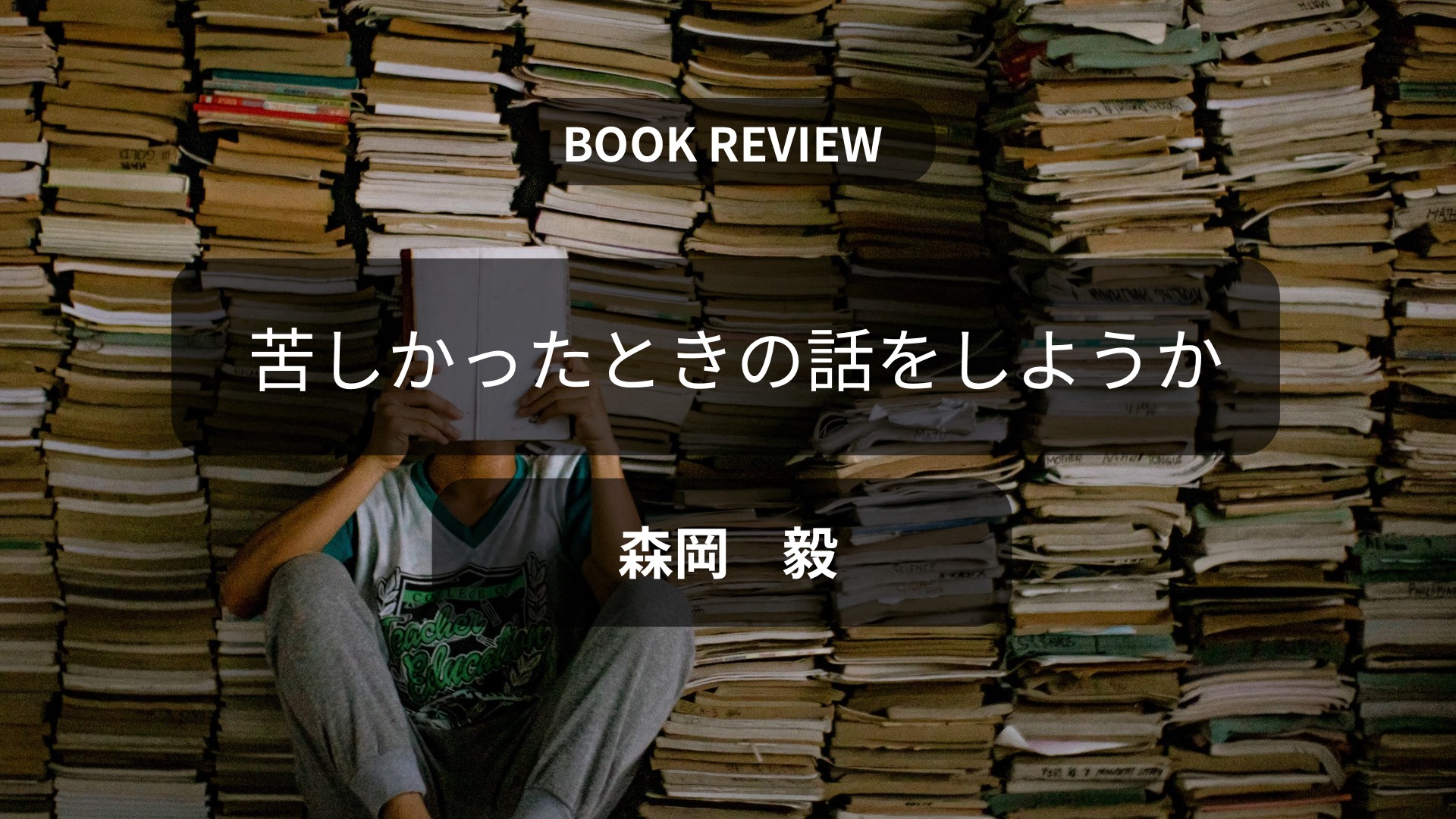
コメントを送信