『映画は父を殺すためにある』島田裕巳(ちくま文庫)2012年
名画とよばれる映画、面白い映画というのは、基本的に物語のなかに通過儀礼が存在し、神話の構造をなぞっているものが多い。本書では、『ローマの休日』、『スタンド・バイ・ミー』、『魔女の宅急便』、『スター・ウォーズ』、『男はつらいよ』など個別の映画のエピソードや構造を参照しながら、各エピソードや構造がどういった役割が与えられているのか、など丁寧に検証されていきます。また、『通過儀礼』、『千の顔を持つ英雄』という二冊の重要な書籍も紹介されています。
《以下、各映画のネタバレ含みます。》
映画は通過儀礼を描く
オランダ人の民俗学者、ヴァン・ジュネップは、20世紀のはじめに『通過儀礼』という本を書き、通過儀礼について最初に理論的な考察を加えます。
ヴァン・ジュネップは、人間の一生、あるいは社会を、数多くの部屋を持つ大きな家にたとえた。人間の一生は、家のなかにある一つの部屋を出て、また別の部屋に連続して移っていくようなものだというのである。人間の一生は、最初は赤ん坊という部屋からはじまる。しかし、永遠にそこにとどまっていることはできず、時期がくれば、次の子どもの部屋へ移っていかなければならない。そのあとには、若者の部屋、既婚者の部屋、中年の部屋、そして老人の部屋と続き、最後には死者の部屋に入っていく。通過儀礼は、新しい部屋に移っていく際に、二つの部屋を隔てる敷居を越えたことを記念して行われる儀礼なのである。
p34
アメリカ人の神話学者、ジョセフ・キャンベルは、世界各地に伝えられている神話を集め、それらが英雄の冒険物語になっていること、共通した筋書きを持っていることを発見し『千の顔を持つ英雄』の中にそれを記します。
キャンベルによれば、神話のなかに登場する英雄は、まず冒険に出発し、危険をおかしながら、人間の力のおよばない世界へ向かい、そこで、超人的な力を備えた敵に遭遇し、それと戦うことになる。英雄は、彼の助けになってくれる人間の援助を受けながら、苦しい戦いを勝ちぬき、敵をうちやぶる。そして最後に、特別な力を授けられて、また元の世界へ戻り、めでたく王女と結ばれることになるのだが、これはまさにアメリカの青春映画の筋書きにそのままあてはまる。
p154
出発、冒険、帰還の三つの段階から構成されている英雄の冒険物語は、通過儀礼における分離、移行、結合の三段階に対応していると著者は解説しています。
ジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ』はまさにこのキャンベルのいう王道中の王道、神話の型をそのまま踏襲していることがわかります。ギリシャ神話やオイディプス王で描かれている「父殺し」が『スター・ウォーズ』ではテーマとなっています。
『ローマの休日』、『スタンド・バイ・ミー』においても、通過儀礼という苦難を通じて、主人公がそれを乗り越え、そして帰還するという成長物語になっています。
通過儀礼の不在~魔女の宅急便~
宮崎駿監督作品の『魔女の宅急便』の章では、なぜ、最後までジジがしゃべれないままなのかを軸に考察されています。
主人公の女の子のキキは、ある事件をきっかけにホウキで飛べなくなるのですが、それと同時に今まで言葉がわかり会話していた黒猫のジジの言葉もわからなくなってしまいます。
ラストにトンボという男の子を救うために必死に頑張っているところで、急に飛べるようになりますが、ジジとは最後まで話すことができません。
本当の矛盾や現実に直面することが回避されているにもかかわらず、キキが通過儀礼を果たしたようにみえるのは、トンボを救うスリリングな場面が用意されているからである。
p99
おソノさんやその夫、おばあさんやトンボ、好意のかたまりのような人物にかこまれ、矛盾や現実に直面しているシーンが存在していないと著者はいいます。なんの前触れもなく、デッキブラシで飛べるようになったことは偶然で、試練に打ち勝っているわけではない。ジジと最後まで言葉を交わせないというのも、物語として矛盾した状況を作り出している。
通過儀礼があることが必ずしも名画の条件であるとは思わないですが、構造的な見方をすると、違和感を感じるのかもしれません。
通過儀礼の不在は、次の『男はつらいよ』でも関連します。
日本的通過儀礼~男はつらいよ~
アメリカ映画が、神話や説話に基づく通過儀礼や型を忠実に再現する一方で、山田洋次監督の『男がつらいよ』は、それに反するパロディのような形になっています。
寅さんは、失恋などの問題にぶつかったとき、問題の起きた場所を捨てて旅に出てしまうため、その問題を試練として受け止め、それを克服していく努力をしない。そこに、井上ひさしが指摘しているように、彼が通過儀礼を果たせず、未熟なままにとどまっている原因がある。
p203
アメリカ映画なら、主人公が通過儀礼を果たしたところで結末を迎える。そして、試練に耐えられず、通過儀礼に失敗した人間には死が用意されている。ところが、『男はつらいよ』では、少なくとも一つの作品を見るかぎりでは、寅さんが成長したようには描かれていない。
p203・204
主人公の寅さんは、若い頃に家出をし、約20年ぶりに故郷の柴又に戻ってくるのですが、テキヤなどで働きつなぎ、失恋と旅を繰り返します。結婚して家庭を築くのでもなく、定職に就くのでもなく、通過儀礼の失敗者として寅さんは存在し続けます。それでも、48作ものシリーズとなり、日本国民に愛され続けている要因として、『男がつらいよ』の視聴者は、通過儀礼による代替的発散ではなくて、不在の感覚によって共感を得ている可能性があります。
僕たちは人生の節目における通過儀礼を経て、新しい自分に生まれ変わっていく。映画はその生まれ変わりの過程をドラマとして描くことによって、人生のモデルを示すとともに、人生の意味を解釈するための枠組みを示唆してくれる。その点では、映画を見るという行為自体も、通過儀礼の意味を持っている。僕たちは、映画とともに一歩ずつ大人への道を歩んでいくことになるのではないだろうか。
p226
※岩波文庫『通過儀礼』は絶版のためプレミアがついています。
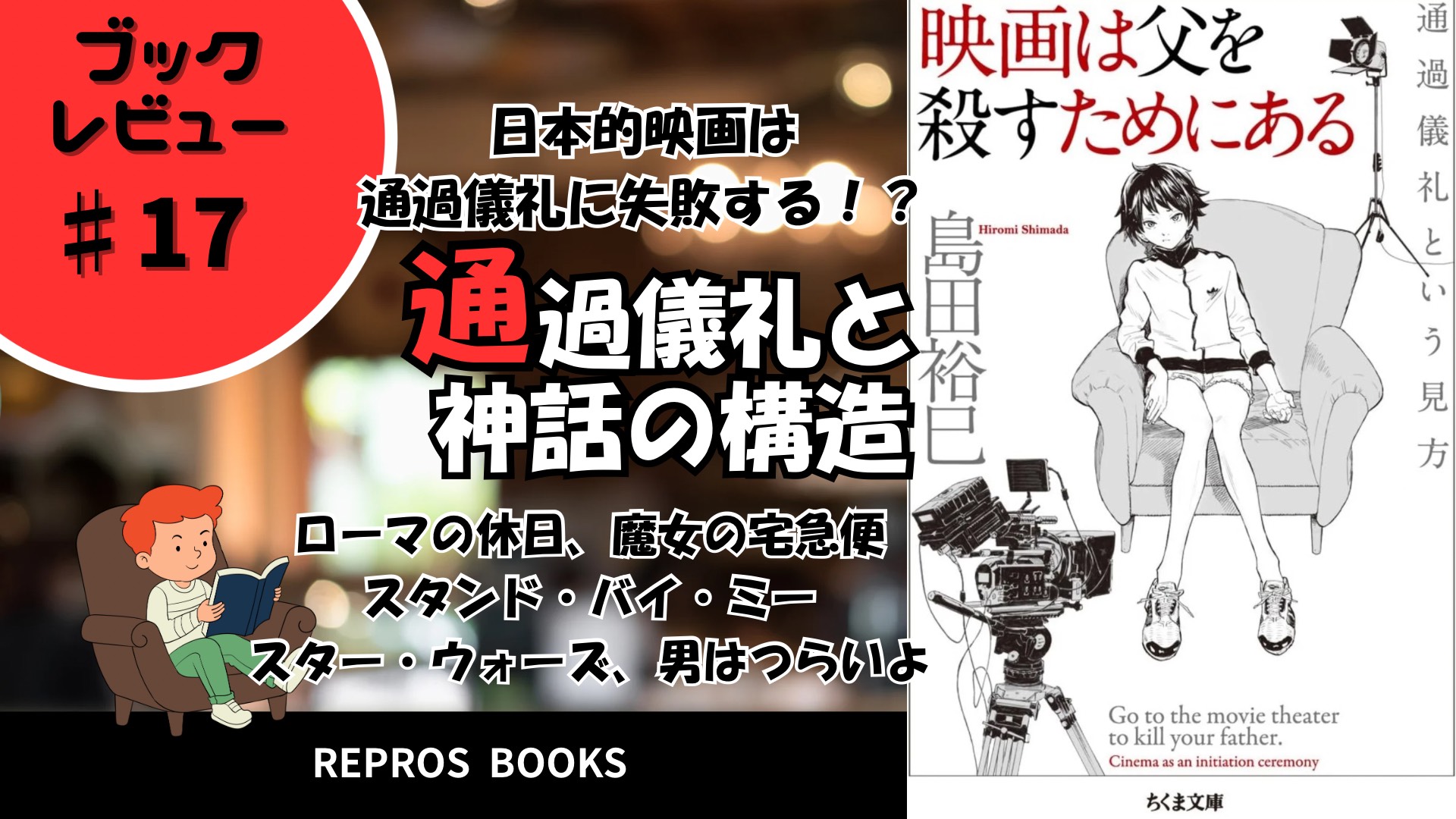
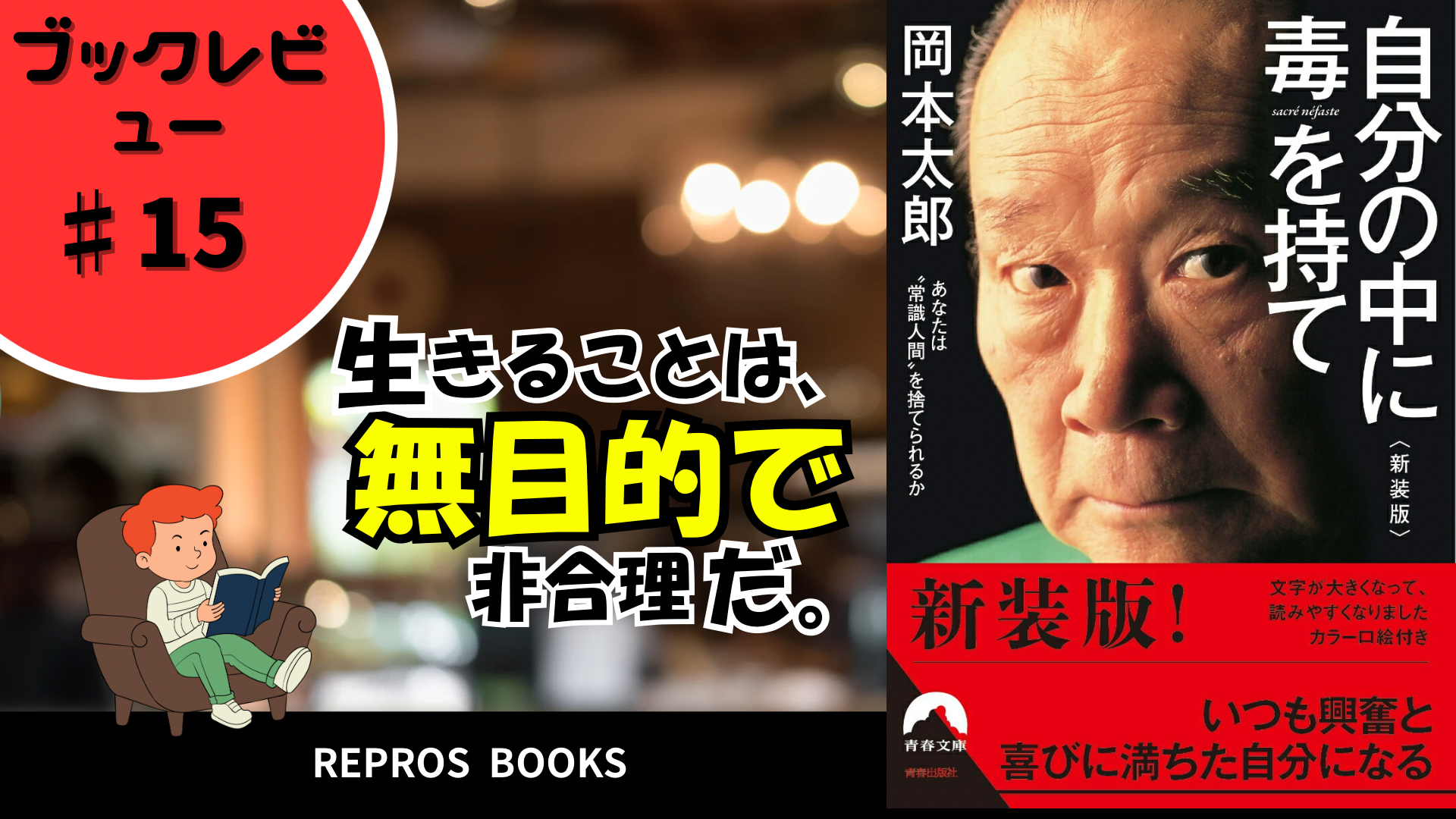
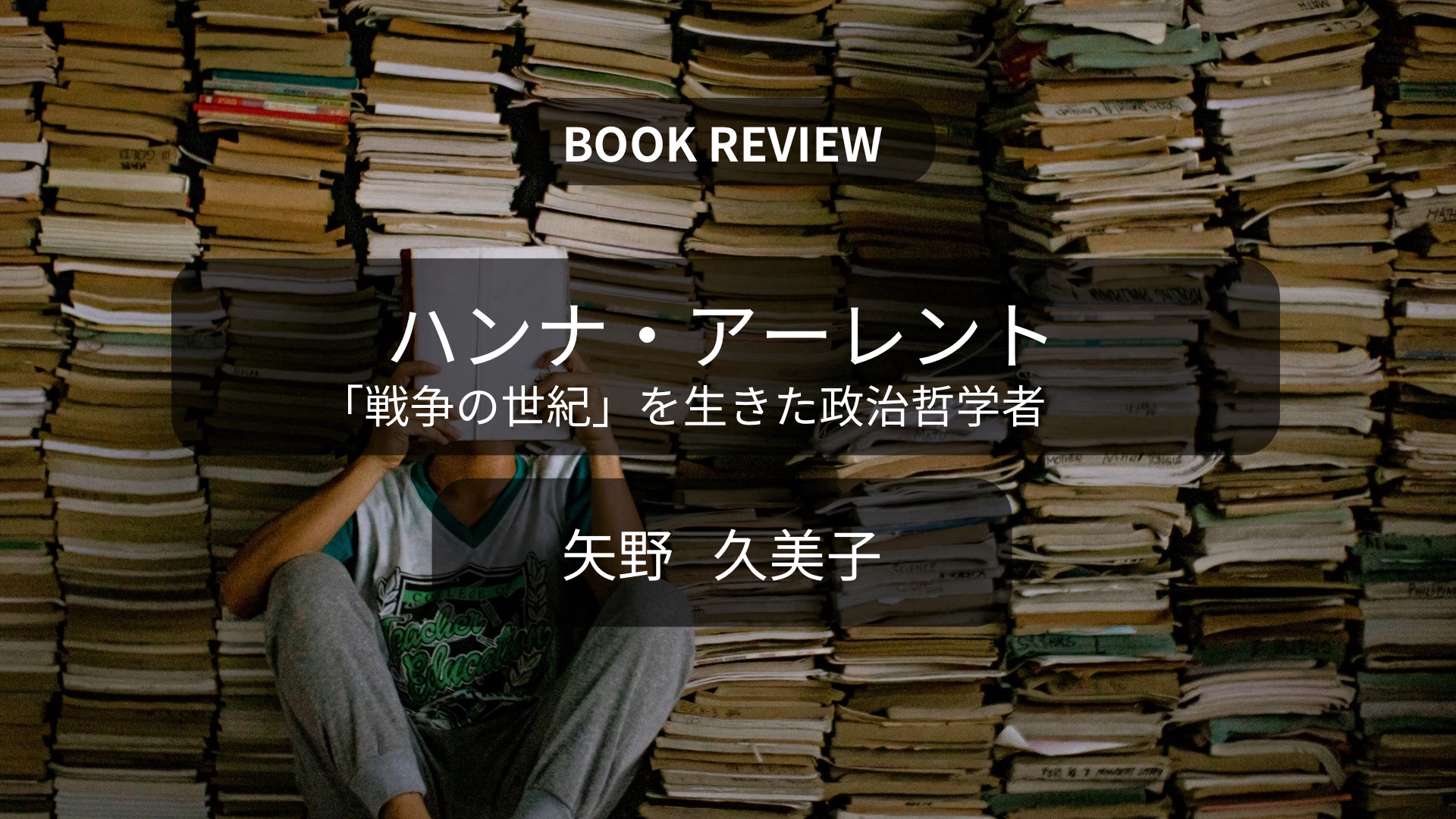
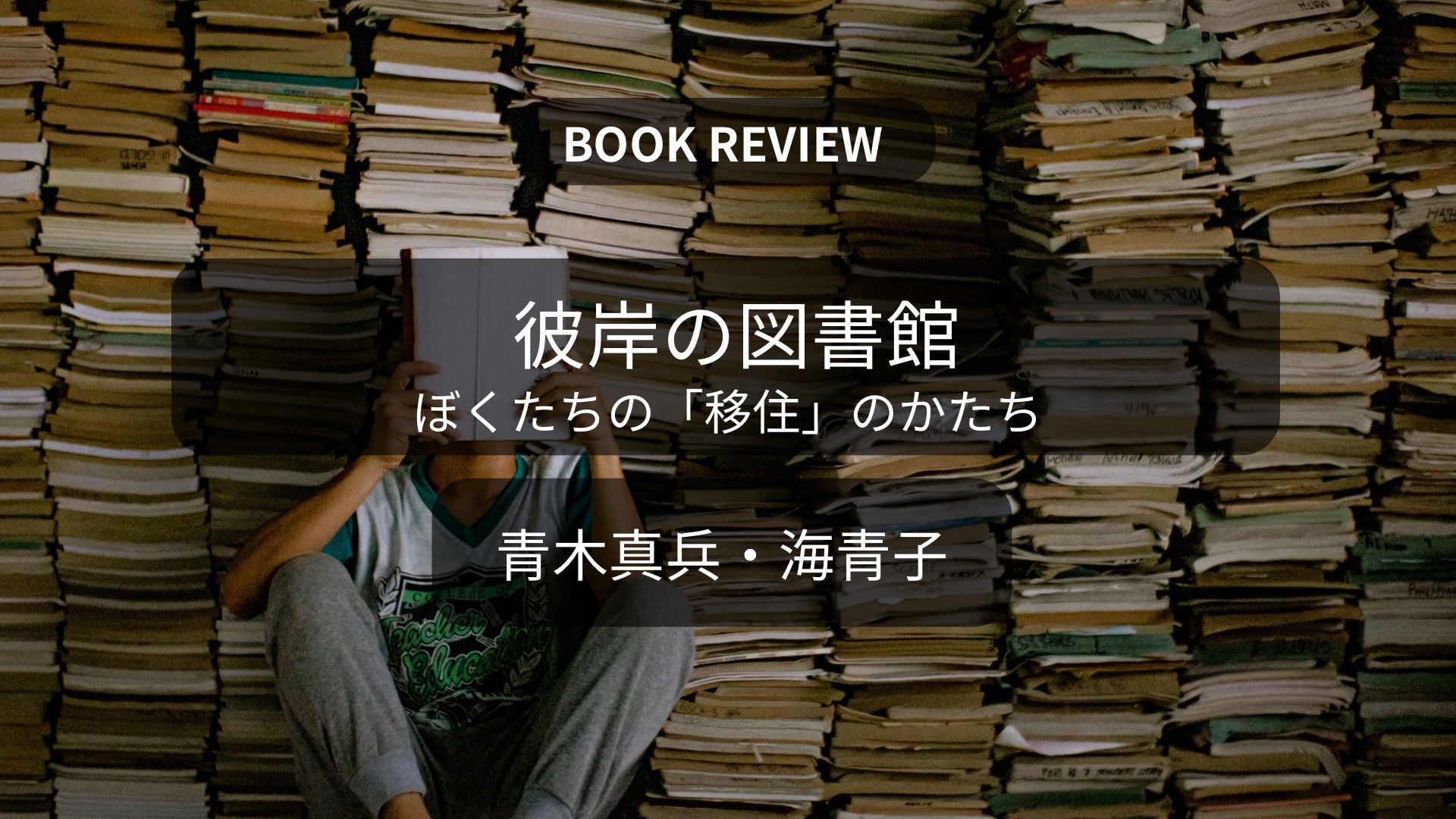
コメントを送信